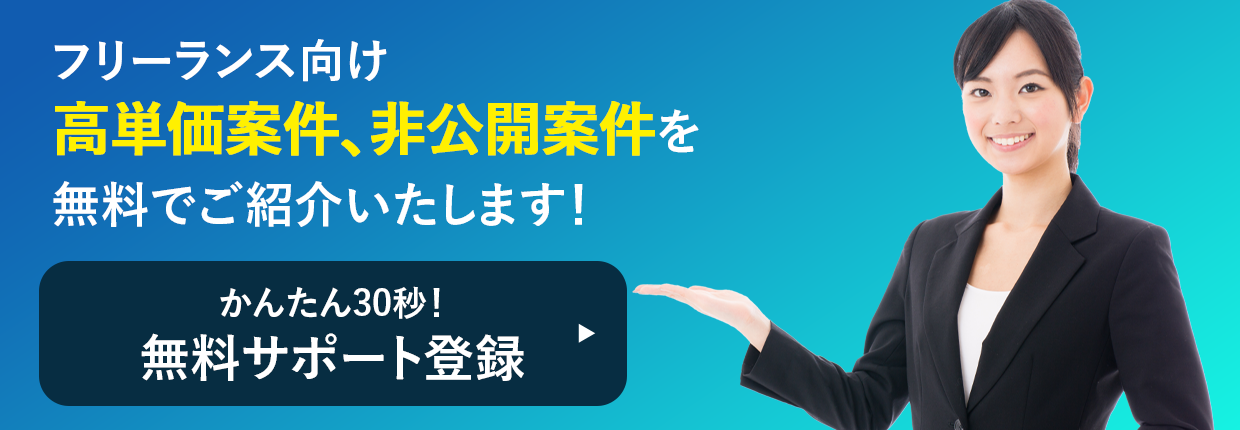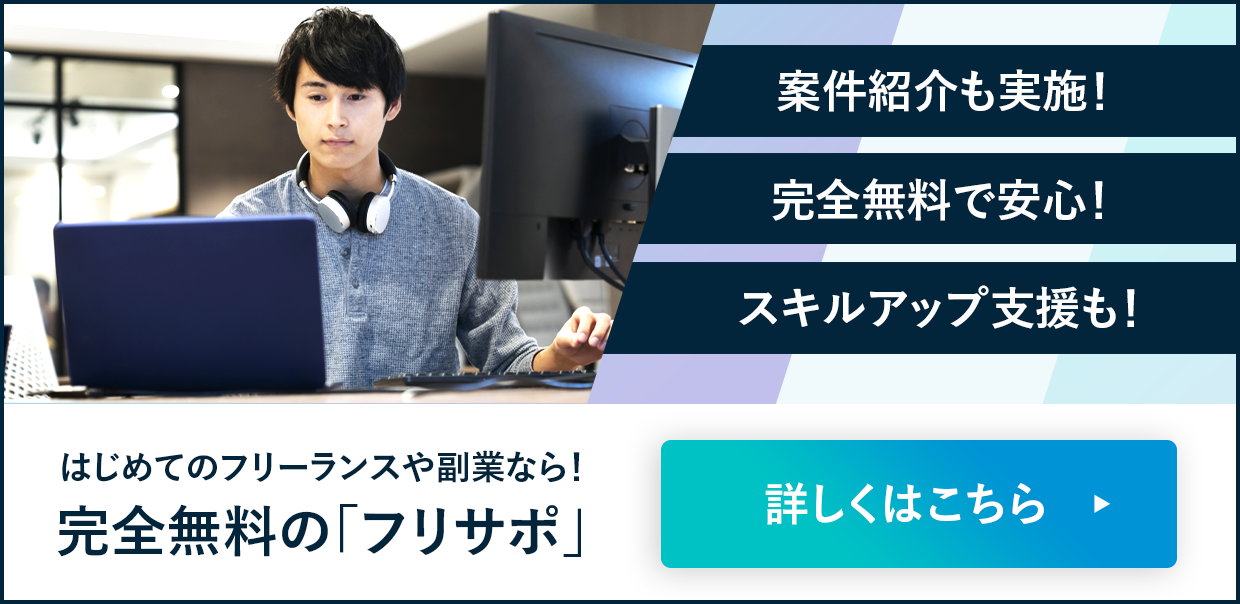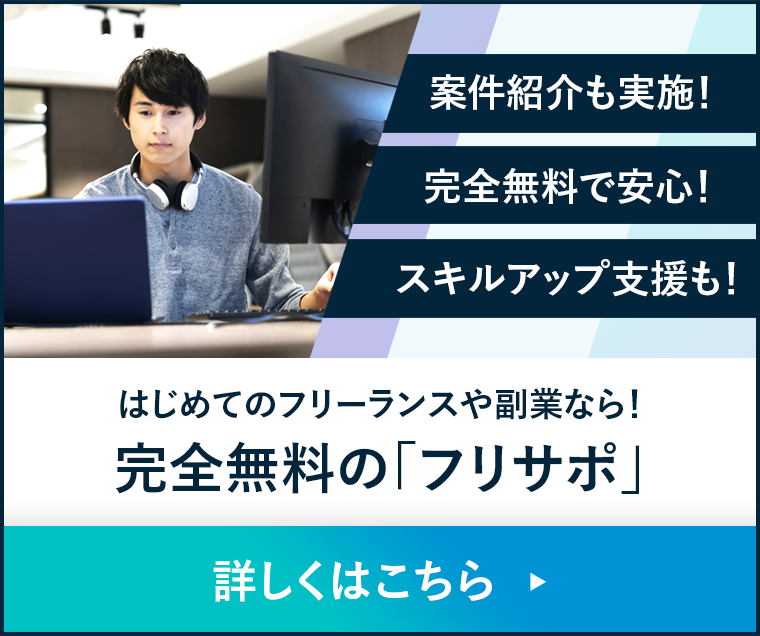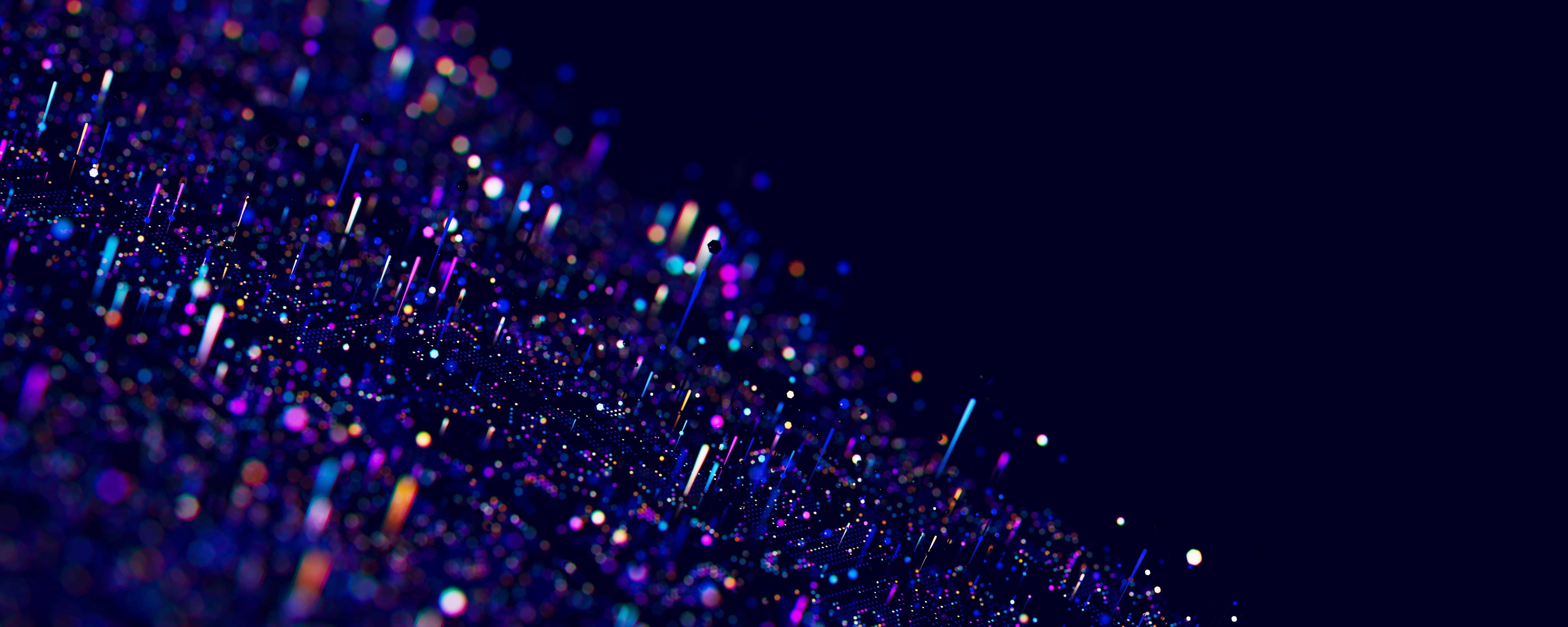RAG(検索拡張生成)とは?仕組みやメリット・デメリットについて解説

近年、生成AIの活用が急速に広がるなかで注目されているのが「RAG(Retrieval-Augmented Generation:検索拡張生成)」です。
ChatGPTをはじめとする大規模言語モデル(LLM)は多様な文章生成に活用されていますが、誤情報(ハルシネーション)や最新情報への対応といった課題を抱えていました。こうした課題を解決する技術として、外部データを取り込みつつ自然な応答を生成できるRAGの導入が進んでいます。
本記事では、RAGの基本的な仕組みから求められる背景、具体的な活用事例、メリット・デメリットまでをわかりやすく解説します。
RAGとは
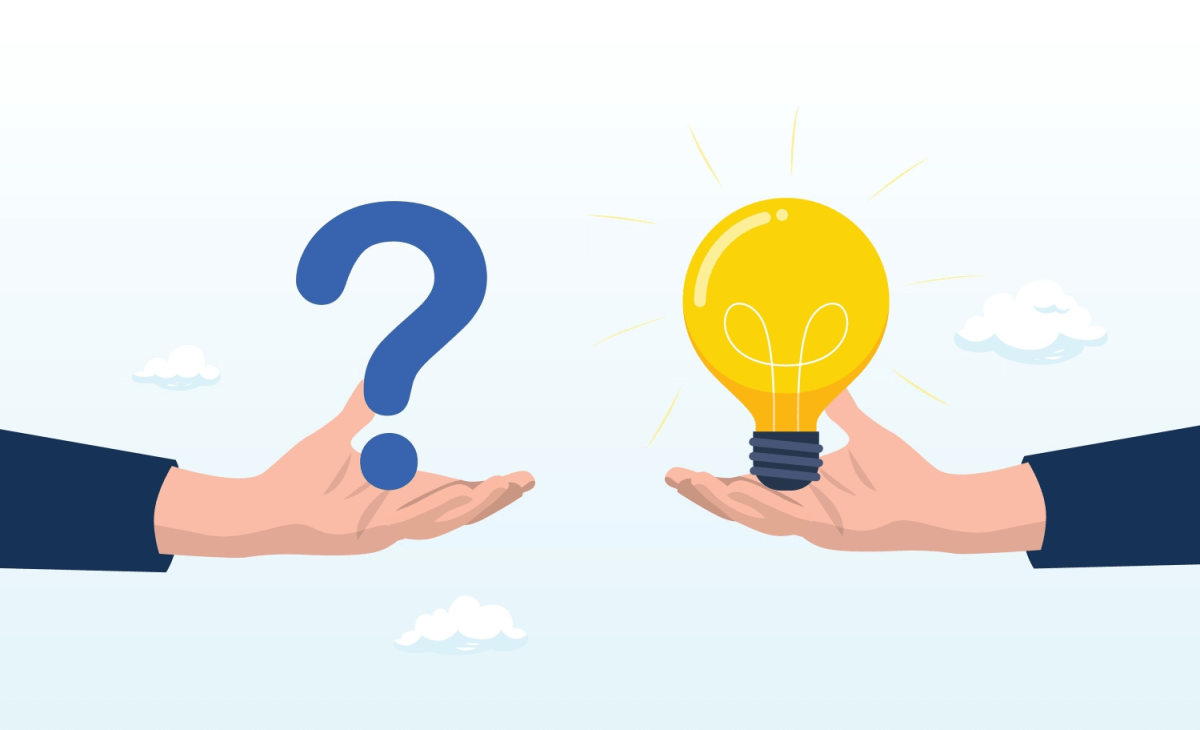
RAGとは「Retrieval-Augmented Generation」の略称で、日本語では「検索拡張生成」と呼ばれます。大規模言語モデル(LLM)に外部の情報検索機能を組み合わせることで、より正確で信頼性の高い応答を生成できる仕組みです。
従来の生成AIは、学習済みデータの範囲で応答を生成するため、学習時点以降の情報には対応できず、また誤った情報をそれらしく提示してしまう「ハルシネーション」の問題がありました。RAGでは、まず外部の知識ベースや文書データから関連する情報を検索し、それをモデルに入力することで回答を補強します。この仕組みにより、最新情報や企業内の独自データを組み込んだ自然な文章生成が可能となります。
たとえば、FAQシステムや社内ナレッジ検索などでは、RAGを導入することで精度の高い回答が得られます。生成AIの利便性を維持しつつ、情報の正確性を強化できる点がRAGの大きな特徴です。
RAGが求められる理由
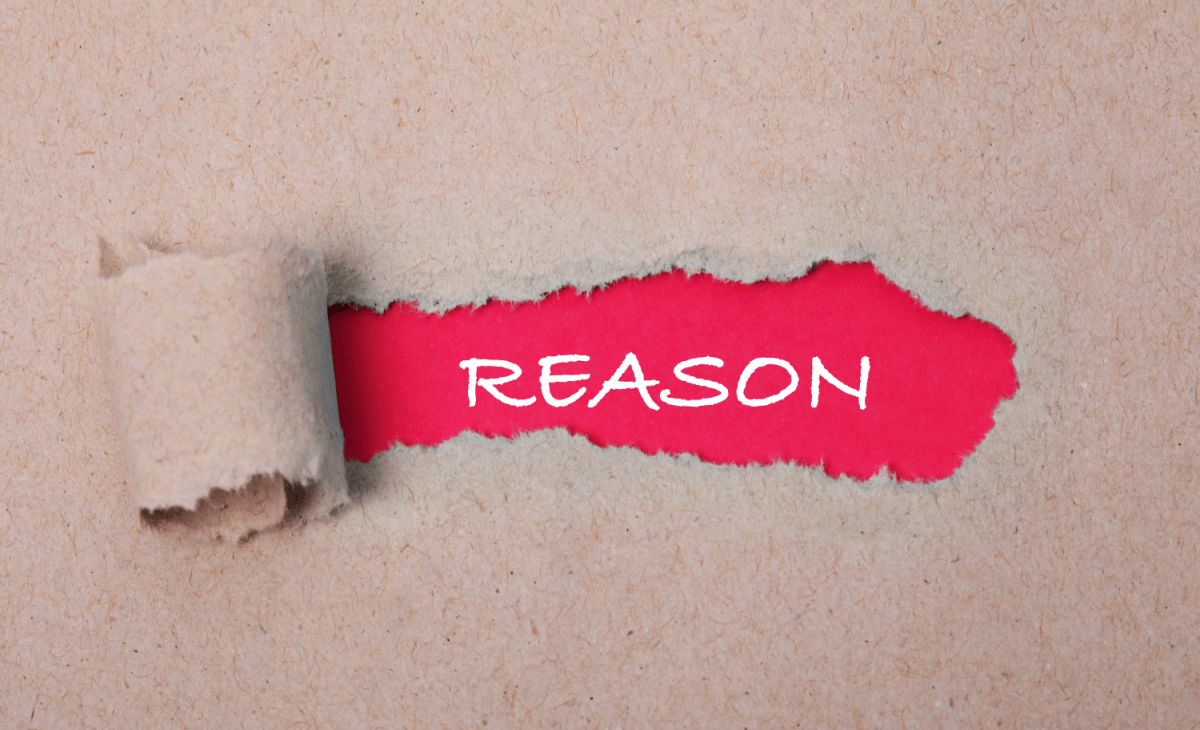
RAGは、従来の生成AIが抱える課題を克服する技術として注目されています。特に「社内データなどの独自情報に対応できる点」と「ハルシネーションを大幅に抑制できる点」が導入を後押ししています。
社内データなど、独自の非公開情報に対応できる
大規模言語モデルは、インターネット上の公開データを中心に学習しているため、特定企業の業務データや非公開資料には対応できません。
そのため、社内マニュアルや業務システムのデータを活用したいケースでは限界がありました。
RAGを導入すると、外部の知識ベースとして社内ドキュメントや業務データを検索対象に組み込めるため、生成AIがそれらを参照しながら回答を出せるようになります。
これにより、FAQ対応、レポート作成、契約書レビューなど、企業固有の知識を反映した活用が可能となり、業務効率化に直結します。
ハルシネーションを大幅に抑制できる
生成AIが出力する誤情報(ハルシネーション)は、実務利用における大きな課題でした。
特に法務や医療、金融など高い正確性が求められる分野では、そのままではリスクが大きすぎると言えます。
RAGは、回答を生成する前に信頼できる情報源から関連データを検索して参照するため、回答の裏付けが強化されます。
これにより、誤情報の発生を大幅に減らし、実務レベルで安心して利用できる環境を整えられるのです。エンジニアにとっては、ユーザー体験の向上やシステム信頼性の確保という観点からも、RAGは不可欠な技術となりつつあります。
RAGの仕組み
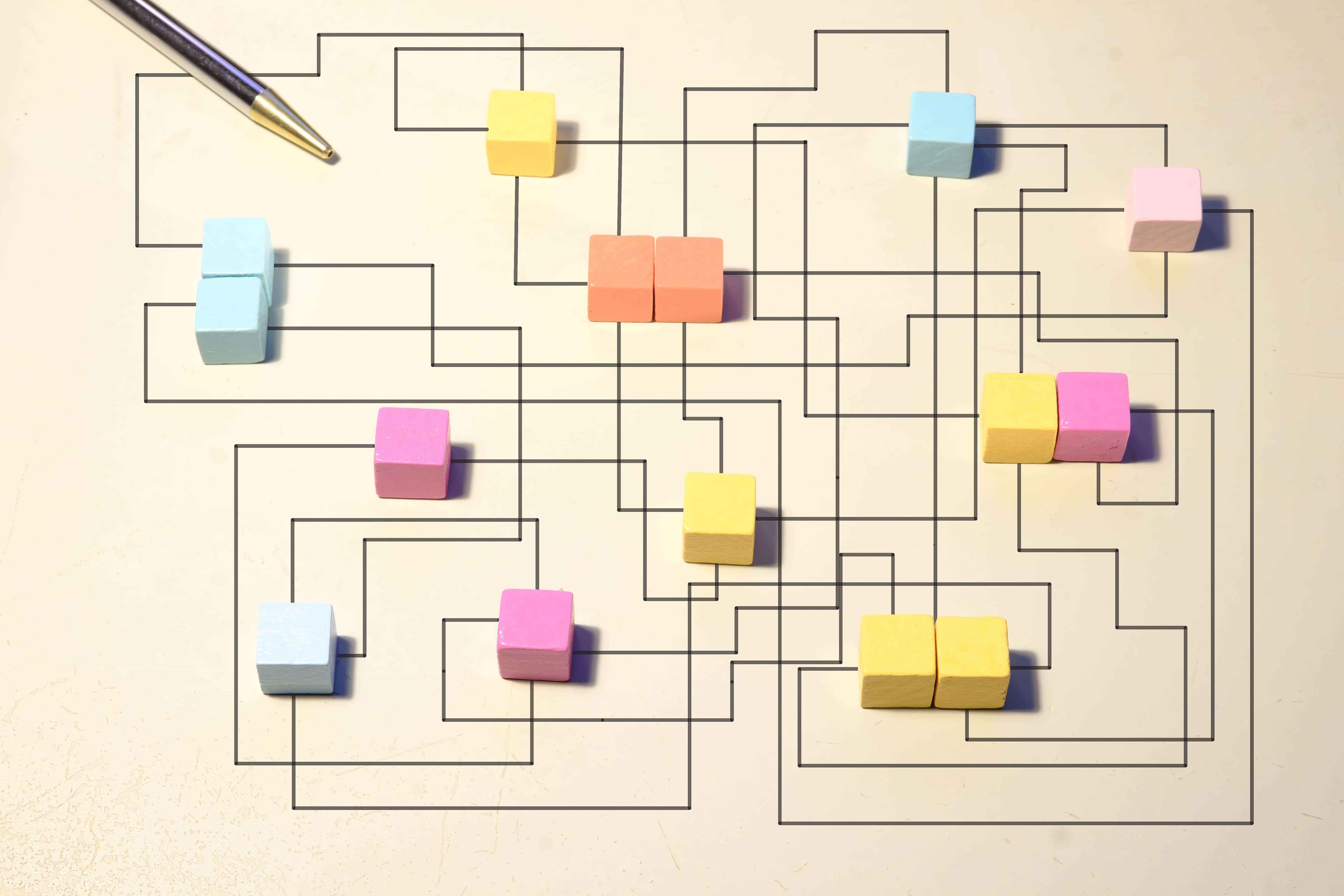
RAGは「検索(Retrieval)」「拡張(Augmentation)」「生成(Generation)」の3つのプロセスを組み合わせて動作します。大規模言語モデルの強力な文章生成能力に、外部データの検索機能を統合することで、精度と信頼性を両立させています。ここでは、それぞれのプロセスに関して順を追って解説します。
検索(Retrieval)
最初のステップは、ユーザーからの質問やリクエストに対して関連する情報を外部データベースから検索することです。
検索対象は、公開Web情報だけでなく、企業のナレッジベースや文書管理システム、論文データベースなど多岐にわたります。この段階で適切な情報を取り出せるかどうかが、最終的な回答の精度を左右します
近年では、ベクトル検索技術やエンベディング*を用いた意味検索が活用され、質問文と意味的に近い文書を効率的に抽出できるようになっています。
*言葉や画像などのデータを、コンピュータが扱いやすい数値のベクトル(座標の並び)に変換すること
拡張(Augmentation)
検索で得られた関連情報は、そのままでは散文的であったり長すぎたりする場合があります。
そこで、回答に必要な情報を整理し、言語モデルが扱いやすい形に加工するのが拡張のステップです。
具体的には、検索結果の要約、関連部分の抽出、フォーマット整形などが行われます。この処理により、モデルは最小限の負荷で必要十分なコンテキストを参照でき、正確な回答生成に繋がります。
生成(Generation)
最後に、大規模言語モデルがユーザーの質問と拡張された情報を組み合わせ、自然な文章として回答を生成します。
この段階では、AIの自然言語処理能力を活かして、利用者が理解しやすい表現や文脈に沿った説明が作られます。RAGの強みは、この生成過程に「最新の検索情報」を取り込める点であり、学習時点以降の情報や独自データを反映した回答が可能となります。
RAGの活用事例
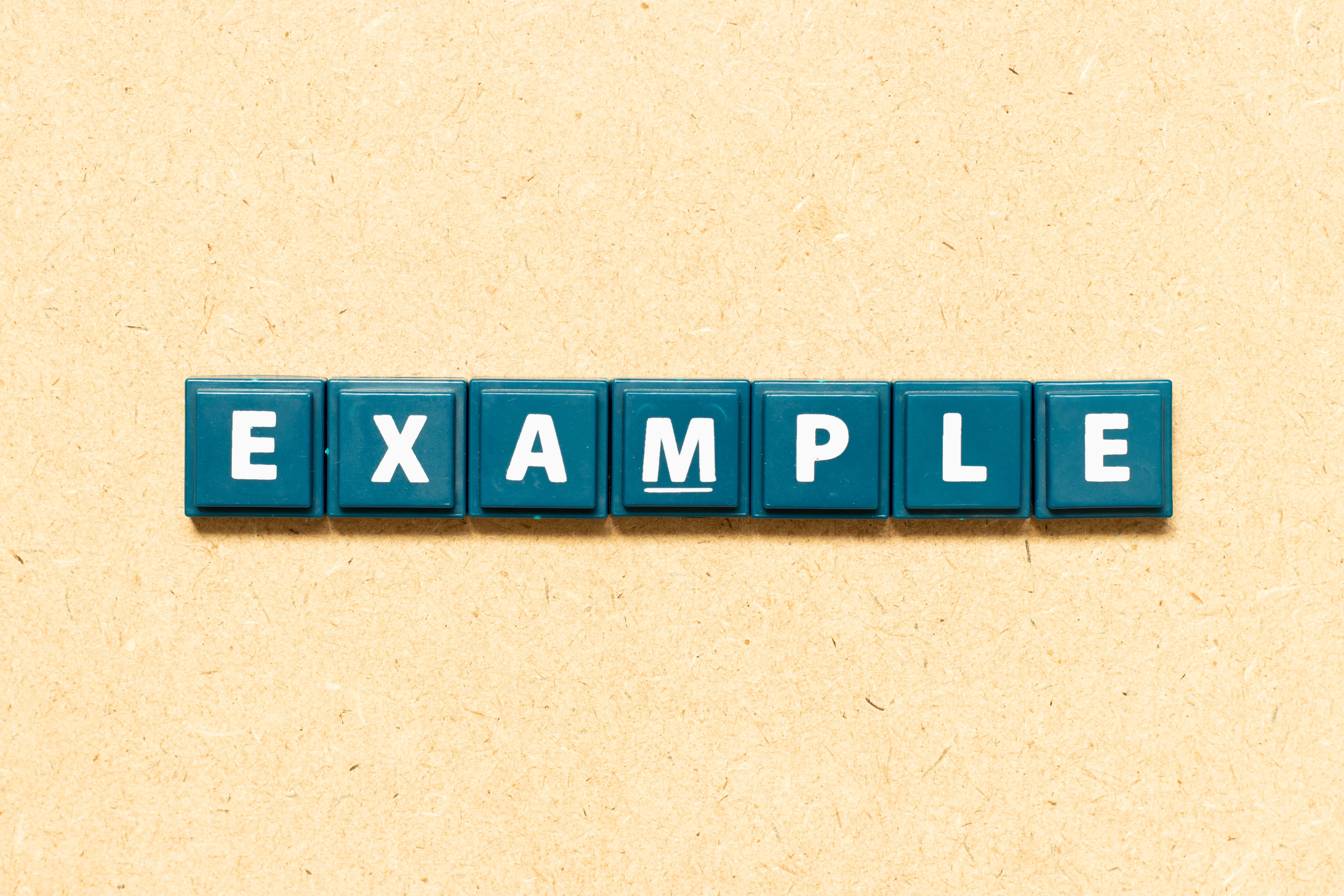
RAGは企業や自治体など、さまざまな組織で導入が進んでいます。特に情報検索や業務効率化が課題となっている分野で効果を発揮しており、実用的な事例も増えてきました。
ここでは代表的な活用事例を3つ紹介します。
静岡県:データ分析や書類の評価・審査などを効率化
静岡県では、行政業務における大量のデータ分析や書類審査を効率化するためにRAGを導入しました。
従来は担当者が膨大な資料を確認する必要がありましたが、RAGを用いることで関連情報を自動検索し、AIが整理した上で回答を提示できるようになりました。
これにより、業務スピードの向上だけでなく、判断の均質化や担当者の負担軽減といった効果が得られています。自治体業務の効率化は全国的な課題であり、この事例は今後の行政DXの参考となるでしょう。
参考:https://exawizards.com/exabase/gpt/case/29639/
住友電気工業株式会社:対話形式で社内情報を収集可能に
住友電気工業株式会社では、社内に蓄積された大量の技術資料やナレッジを有効活用するためにRAGを導入しました。
従来は必要な情報を探し出すのに時間がかかっていましたが、RAGにより自然言語で質問するだけで関連資料を検索・要約できるようになりました。
これにより、技術者が迅速に情報へアクセスでき、研究開発や業務改善のスピードが大幅に向上しました。社内知識を活用した生産性向上の好例といえます。
参考:https://www.sei-info.co.jp/quicksolution/cases/sei-rag/
東洋建設株式会社:労働災害防止
東洋建設株式会社では、建設現場における労働災害防止を目的としてRAGを活用しています。
現場作業に関連する安全マニュアルや過去の事故事例をAIに検索・参照させることで、作業員が迅速に必要な情報を確認できる仕組みを構築しました。
これにより、現場の安全意識が高まり、事故防止につながる効果が期待されています。建設業のように安全管理が重要な業界において、RAGの実用性を示す具体例です。
参考:https://www.toyo-const.co.jp/topics/technicalnews-20676
RAGのメリット

RAGは、大規模言語モデル単体では解決が難しかった課題を克服できる点が大きな魅力です。業務利用やサービス実装を検討するうえで、次のようなメリットが期待できます。
生成結果の信頼性が高まる
RAGは回答を生成する際に、外部データベースから取得した関連情報を組み込むため、根拠のある回答が可能となります。
これにより、従来の生成AIが抱えていた「もっともらしいが誤った回答」を大幅に減らすことができます。
特に、法務・医療・金融といった正確性が不可欠な分野では、信頼性向上の効果が非常に大きいといえます。ユーザーにとっても「どの情報を参照したのか」が明確になれば、安心して利用できる環境が整います。
外部情報の更新が容易に行える
RAGでは、学習済みモデルを再学習させるのではなく、検索対象のデータベースを更新することで最新情報を反映できます。
たとえば新しい製品情報や規制変更があった場合でも、データベースを更新すれば即座に生成結果に反映されます。
これにより、最新情報を必要とするFAQシステムや顧客対応チャットボットの精度を維持しやすくなります。エンジニアにとっては、モデル再学習に伴うコストや時間を削減できる点も大きなメリットです。
費用対効果の向上
従来の生成AIでは、学習データの更新や追加学習に膨大なコストがかかりました。
RAGを利用すれば、既存のモデルに検索機能を追加するだけで、必要な情報を反映した応答が可能となるため、開発・運用コストを抑えつつ高精度なシステムを構築できます。結果として、少ない投資で高い成果を得やすくなり、費用対効果が向上します。
特に、企業独自の情報活用を進めたい場合には、RAGは効率的な選択肢となります。
RAGのデメリット

RAGには多くのメリットがある一方で、導入や運用にあたって注意すべき課題も存在します。システム設計や実装に取り組むエンジニアは、これらのデメリットを理解したうえで対策を講じる必要があります。
学習データの用意や実装までの時間がかかる
RAGは外部データを検索対象とする仕組みであるため、検索対象データベースの整備が欠かせません。
社内文書やナレッジを活用する場合、データの収集・整理・クリーニングが必要であり、その準備には時間と手間がかかります。
また、検索精度を高めるためにデータをベクトル化する仕組みを導入するなど、技術的な実装負荷も発生します。小規模なPoC(概念実証)から始めることは可能ですが、本格的な業務システムとして運用するには一定の準備期間が必要です。
回答速度が遅い場合がある
RAGは、ユーザーの質問に回答する際に「検索→拡張→生成」という複数ステップを踏むため、通常の生成AIより応答に時間がかかることがあります。
特に検索対象データが膨大な場合や、検索アルゴリズムが最適化されていない場合には、ユーザー体験を損なう恐れがあります。
リアルタイム性が重視される業務やサービスに導入する際には、インデックス構造の工夫やキャッシュ利用など、パフォーマンス改善の工夫が求められます。
まとめ
RAG(検索拡張生成)は、大規模言語モデルの弱点である「最新情報への対応不足」や「ハルシネーション」を解消できる技術として注目を集めています。
検索・拡張・生成という3つのステップを組み合わせることで、信頼性の高い回答を実現し、企業のナレッジ活用や業務効率化に大きな効果をもたらします。実際に、自治体や大手企業でも導入が進み、実用性が確認されています。
一方で、データ整備や実装コスト、回答速度の課題もあるため、導入を検討する際には自社の利用シーンや目的を明確にすることが重要です。
PoC(概念実証)から小規模に始めて段階的に拡大するアプローチが、現実的でリスクの少ない進め方といえるでしょう。
RAGは、今後ますます普及が進む生成AIの実務活用を支える基盤技術です。最新の動向を把握し、適切に導入することで、ビジネスの競争力を大きく高められる可能性があります。
これからRAGを活用した副業やプロジェクトを探したい方は、BIG DATA NAVI への登録がおすすめです。豊富なAI・データ関連案件の中から、自分に合った仕事を見つける第一歩を踏み出しましょう。
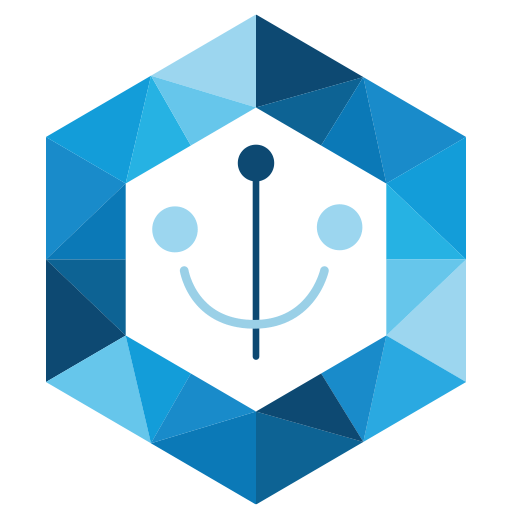
AIを仕事にするためのキャリアノウハウ、機械学習・AIに関するTopics、フリーランス向けお役立ち情報を投稿します。

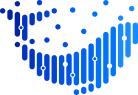 フリーランス求人を探す
フリーランス求人を探す