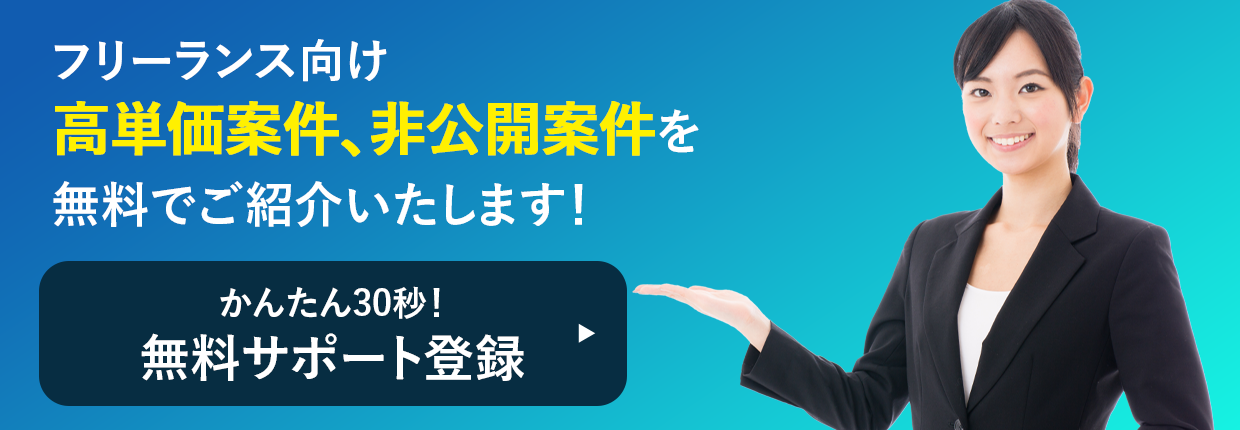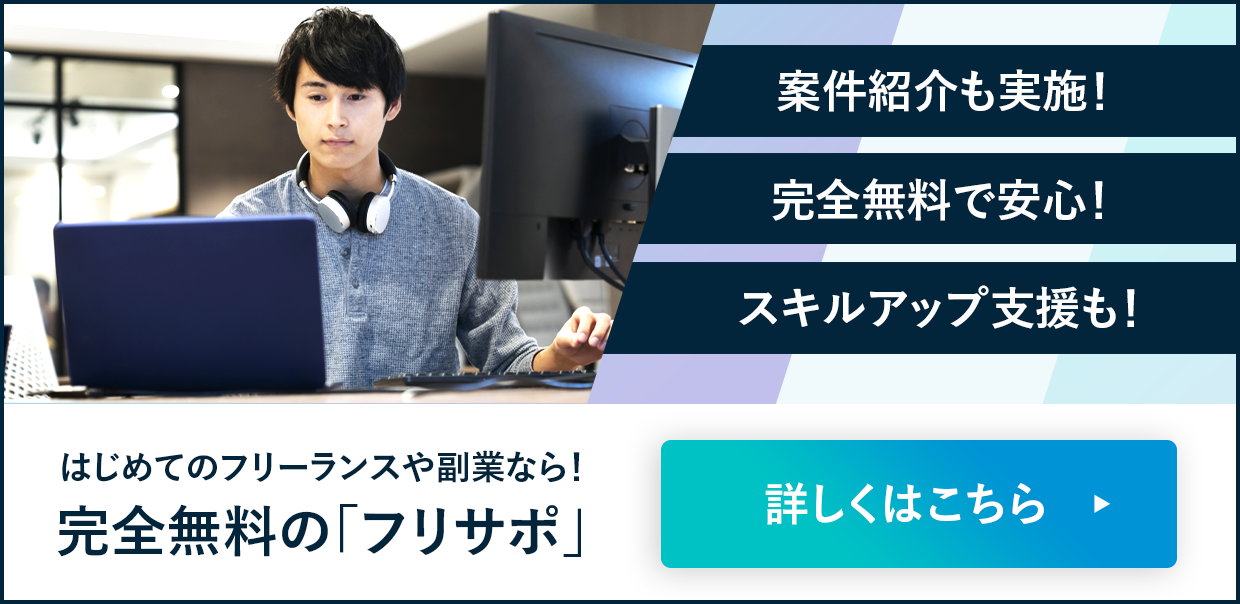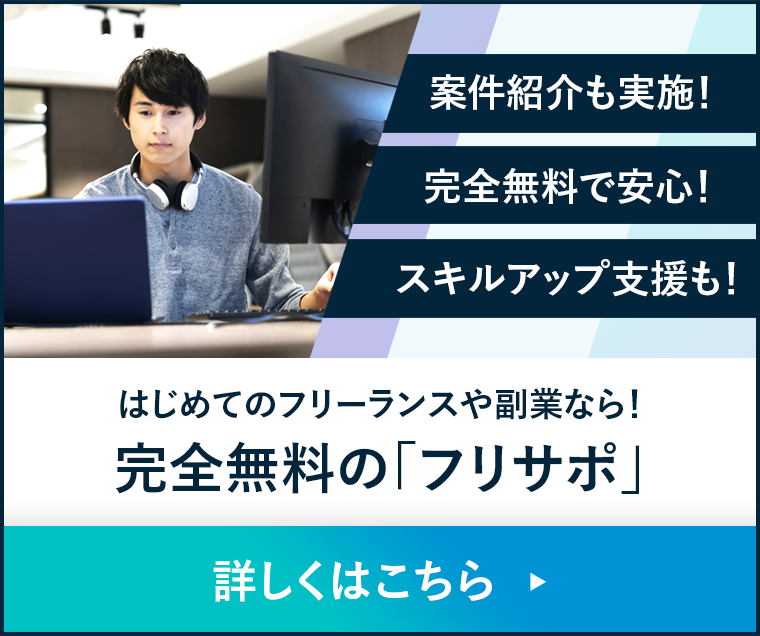Kaggleとは?登録方法や機能、コンペに参加するメリット・デメリットについて解説

Kaggleは「スキルを磨ける」「実務に近い経験が積める」といった理由から、多くの学習者やエンジニアに注目されているプラットフォームです。
ただ、「コンペに参加するのは難しそう」「英語が多くて取っつきにくい」と感じる方もいらっしゃるのではないしょうか。
本記事では、Kaggleの特徴・登録方法・主な機能・コンペ参加に参加するメリットやデメリットを、初心者にもわかりやすく解説します。
目次
Kaggle とは
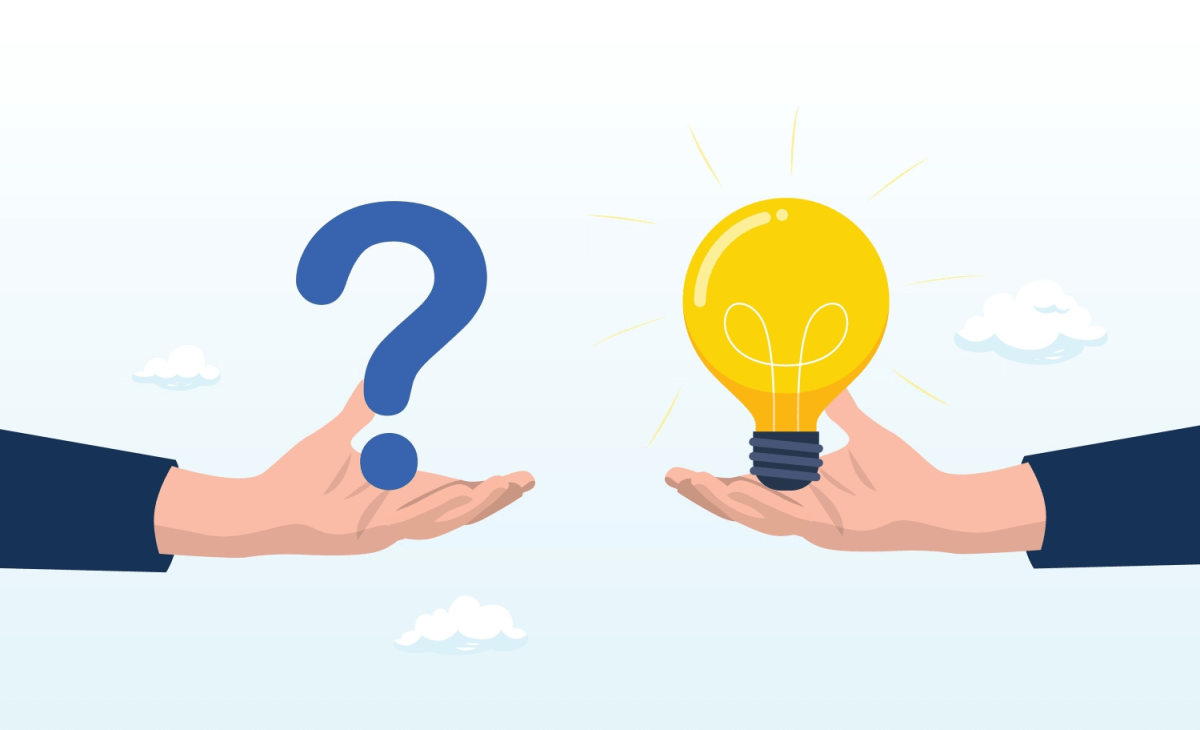
Kaggle(カグル)は、Googleが提供するデータ分析・機械学習のためのオンラインプラットフォームです。世界中のデータサイエンティストが集まり、企業や団体が出題する課題に挑戦したり、公開されたデータセットを使って自由に分析を行ったりと、幅広い目的で活用されています。
なかでも注目されているのが、Kaggle上で開催されている機械学習コンペティションです。参加者は、企業や団体が提供する実データをもとに予測モデルを構築し、ランキング形式で競い合うといった内容になっています。
多くのコンペでは、上位入賞者(通常は1位~3位程度)に賞金が用意されており、実績が就職・転職活動などで高く評価されることもあります。
とはいえ、Kaggleはプロだけの場所ではなく、初心者でも利用しやすい環境が整えられています。
例えば、チュートリアル形式で学べる教材が用意されていたり、他の参加者が投稿したコード(ノートブック)を閲覧できたりします。
Kaggleの登録方法

Kaggleは、Googleアカウントがあれば誰でも簡単に登録できます。
登録の手順は、以下の通りです。
- 公式サイトにアクセスする
- Googleアカウントでログインする
- プロフィール情報を設定する(任意)
- 登録完了
Kaggleのトップページ(https://www.kaggle.com)を開きます。
右上の「Sign In」または「Join Kaggle」をクリックし、Googleアカウントを選択します。
なお、KaggleはGoogle提供のサービスのため、Googleアカウントがない場合はあらかじめ作成しておく必要があります。
初回ログイン後に、ユーザー名や所属、プロフィール画像などの設定画面が表示されますが、後から入力できるのでスキップしても構いません。
また、実名での登録に抵抗のある方は、ハンドルネームを使用しても大丈夫です。
登録が完了すれば、コンペへの参加、データセットの閲覧、ノートブックの作成など、すべての基本機能が利用可能になります。
Kaggleの機能

Kaggleには、学習から実践までを支えるさまざまな機能が用意されています。
ここでは、Kaggleの主要な機能を5つに分けて紹介します。
Kaggle Rankings
Kaggleには、ユーザーの活動内容に応じて評価が与えられるランキングシステムがあり、「Novice」から「Grandmaster」まで、以下のようにランクづけされています。
- Novice
- Contributor
- Expert
- Master
- Grandmaster
このランクは、コンペでの成績だけでなく、ノートブックやディスカッションへの投稿、データセットの共有など、総合的な貢献度によって上がっていきます。
また、称号はスキルや実績の目安として利用され、Kaggle内外での自己アピールに活用することもできます。
Competitions
Competitions(コンペティション)はKaggleのもっとも有名な機能で、企業や団体が提供するデータをもとに参加者が機械学習モデルを構築し、予測精度を競い合う内容になっています。
また、コンペには賞金が用意されているものもあり、上位入賞者には数千〜数万ドルの報酬が支払われることもあります。
さらに、企業の採用担当者がKaggleの成績をチェックしていることもあり、転職や副業案件獲得の際に実力を示すポートフォリオとしても活用できます。
Datasets
Kaggleには、誰でも自由に使える高品質なデータセットが数多く公開されています。
マーケティング、医療、金融、画像、自然言語など、公開されているデータの分野は多岐にわたり、初心者から上級者まで幅広く活用できます。
データはCSV形式で提供されていることが多く、Kaggle内のノートブックと連携して、すぐに分析を始められるのが特徴です。
また、自分で作成したデータセットをアップロードし、世界中のユーザーと共有することも簡単にできます。
Code
Codeはかつて「Kernels(カーネル)」と呼ばれていたクラウド上のプログラミング環境です。Kaggle内でPythonやRのコードを記述・実行・共有でき、Google Colabのような感覚で扱うことができるのが特徴です。
また、コードはNotebook形式で保存され、他ユーザーの分析手法やモデル構築の過程をそのまま見ることもできます。誰でも見ることができるので、初心者はまず優れたノートブックを「Fork(コピー)」して、自分の環境で試してみるのもおすすめです。
Discussion
Discussion(ディスカッション)は、Kaggleユーザー同士が情報交換できる掲示板のような機能です。
コンペに関する質問や戦略、使用ライブラリの共有、バグ報告、初心者の疑問投稿など、初心者から上級
者まで幅広い層に役立つ情報が扱われています。
英語が中心ではありますが、日本人ユーザーも一定数いるので、内容次第では日本語でやり取りすることも可能です。
また、投稿に対する投票やコメントで評価される仕組みもあり、有益な発信をすると称号アップにもつながるので、積極的に参加するのがおすすめです。
Kaggleのコンペに参加して投稿するまでの流れについて
Kaggleのコンペティションに参加する際は、以下のように7つのステップを順に進めていく必要があります。
①参加するコンペを選ぶ
最初のステップは、自分のレベルや興味にあったコンペを選ぶことです。
Kaggleには様々なテーマのコンペが募集されていますが、初心者の場合は「Titanic」や「House Prices」などの定番コンペから始めるのがおすすめです。これらはデータの構造がシンプルで、解説記事や参考ノートブックも充実しているため、学びながら進めやすいため、初心者でも取り組みやすいのが特徴です。
探し方がわからない場合は、トップページの「Competitions」タブを開いて、開催中・初心者向けなどの条件でフィルタをかけてみると、目的に合ったコンペが見つかりやすくなります。
②参加規約へ同意する
コンペを開くと、最初に表示されるのが「Rules(ルール)」のページです。これは利用規約のようなもので、提出回数の制限やチーム編成ルール、禁止行為などが記載されています。
規約に同意しなければコンペに参加できないため、内容を確認したうえで「I Understand and Accept」ボタンをクリックしましょう。
③データや提出ルールの確認する
次に、データと提出ルールを確認します。「Data」タブで配布されているファイルを確認することができ、「Evaluation」タブでは使用されるスコア指標をチェックできるようになっています。
また、「Submission」タブには提出ファイルの形式や命名規則、締切日などの詳細が記載されています。これらを見落とすと評価が行われないこともあるので、コンペに参加する際はよく確認しておく必要があります。
④学習モデルを作成する
データや提出ルールを理解したら、前処理・特徴量の作成・モデルの学習といったステップを踏みながら、実際に学習モデルの作成を進めていきます。
コードの実行は、Kaggle内の「Notebook(旧Kernels)」を使えば、ブラウザ上で完結します。
また、他ユーザーのNotebookを参考にしつつ自分の理解を深めながら進めていくと、インプット・アウトプットが同時にでき、学習としても効率が良いです。
⑤提出ファイルを作成する
予測が完了したら、提出用ファイルを作成します。多くのコンペでは「id列+予測値1列」のCSV形式で提出するよう指示されます。
ただし、コンペによって提出形式が異なり、形式が間違っているとエラーになるため、必ず「Submission」タブのサンプル提出ファイルを確認しておく必要があります。
⑥提出ファイルを投稿する
完成したファイルを「Submit Predictions」ボタンからアップロードすれば提出が完了します。提出後はKaggleが自動でスコアを計算するので、Public Leaderboardに順位が反映されるのを待ちます。
なお、提出は無制限位できるわけではなく「提出は1日に数回まで」といった回数制限が設けられているので注意が必要です。
⑦評価を確認する
提出が完了すると、スコアと順位がPublic Leaderboardに反映されます。これは公開されている一部のテストデータを使って算出されたもので、他の参加者との相対的な位置を確認できます。
ただし、コンペの最終順位は「Private Leaderboard」によって決まります。締切後、あらかじめ非公開にされていた別のテストデータを使って再評価が行われ、その結果が最終順位として確定します。
Publicで高順位でもPrivateでは順位が大きく変動することもあるので、本番データでも安定したスコアが出せるモデルを目指す必要があります。
初心者がKaggleを使うには

Kaggleは上級者やプロも多数在籍していますが、初心者も気軽に参加できる場所です。
ここでは、初心者がKaggleを活用するための3つの方法をご紹介します。
Kaggle Learnで勉強する
初めてKaggleを使う方は、まず「Kaggle Learn」に触れてみるのがおすすめです。Kaggle Learnは、PythonやPandas、機械学習などを実際にコードを書きながら学ぶことができるオンライン教材です。
内容はすべて英語ですが、スライドと演習がセットになっているので視覚的に理解しやすいのが特徴です。
また、1レッスンあたり10〜15分程度で完結するので、初心者がつまづきやすいポイントから実践的な内容まで、スキマ時間を活用して学習することができます。
Kernels(カーネル)で勉強する
Kaggleでは、他のユーザーが投稿したノートブック(旧称:Kernels)を読むことができます。実際のコンペ参加者が使った分析手法やモデル構築の工夫などが、そのまま公開されているため、実践的な学習として非常に有効です。
ノートブックはデータの扱い方や考え方を学ぶ教材としても優秀なので、気になるものがあれば「Fork」して自分の環境で動かしてみるのもおすすめです。
終了したコンペに取り組む
いきなり本番のコンペに挑むのが不安な場合は、終了したコンペに取り組むのがおすすめです。Kaggleではすでに終了した過去のコンペも公開されているので、データや評価方法、上位入賞者のノートブックなどを自由に閲覧することができます。
初心者は「何をすれば良いかわからない」状態になりやすいものです。まずは他の参加者のノートブックを読みながら、どんな流れで進めているのか、どういう視点でモデルを組んでいるのかをざっくり追ってみるだけでも、ある程度感覚がつかめます。
Kaggleのコンペに参加するメリット

Kaggleのコンペに参加するメリットは、賞金や称号だけではありません。
ここでは、Kaggleのコンペに参加することによって得られるメリットを3つご紹介します。
実際のビジネス課題に取り組める
Kaggleで出題される課題は、企業や団体が実際に直面している問題がベースになっていることが多く、現場に近いテーマに触れられるのが特徴です。
たとえば、医療データをもとに病気のリスクを予測したり、工場の機器の故障を検知したりと、机上の理論では学べない「実務感覚」を養うことができます。
世界中のデータサイエンティストとつながれる
Kaggleには、初学者からトップクラスのプロフェッショナルまで、世界中のユーザーが参加しています。コンペのディスカッションやノートブックでは、他の参加者の視点やアプローチに触れることができ、自分では思いつかない発想を得られる場面も多いです。
また、チーム戦が可能なコンペでは、実際に誰かと協力して問題に取り組むこともできるため、世界中のデータサイエンティストとつながれる点も、Kaggleの魅力といえます。
自分のスキルを客観的に評価してもらえる
Kaggleのコンペでは、提出ファイルに対してスコアが即時に付けられ、その精度によって自分の順位が明確に見える仕組みになっています。
「なんとなくできている」「なんとなく気に食わない」ような感覚ベースではなく、数字で成果が可視化されるため、改善すべき点が明確になります。
また、ランキングやメダルの獲得は、実力の裏付けとしてわかりやすく評価されやすいため、ポートフォリオとして活用したり、転職活動でアピール材料にすることもできます。
Kaggleのコンペに参加するデメリット

Kaggleは学習として非常に有効なプラットフォームですが、使い始めの段階でつまずきやすかったり、評価にこだわりすぎて本質を見失ってしまうこともあります。
ここでは、Kaggleのコンペに参加するデメリットを2つお伝えします。
初心者にはハードルが高い
Kaggleのコンペは初心者でも気軽に参加できる一方で、上級者やプロレベルの参加者も多いためハードルを高く感じやすいです。
特に、高額報酬が設定された本格的なコンペでは、モデルの精度を少しでも上げるために、複雑なアルゴリズムや独自の工夫が求められることもあり、スコアが思うように伸びない場合もあります。
しかし、いきなり上位を目指す必要はありません。最初はノートブックを参考にしながら「試しに動かしてみる」「とりあえず提出して評価を見てみる」といった簡単な行動をするだけでも、初期の学習としては十分効果があります。
ランキングや評価に振り回されることがある
工夫して作成したモデルの順位が上がると大きな達成感がありますが、スコアの変動に一喜一憂したり、結果ばかりを意識しすぎていると、かえって疲れてしまうこともあります。
また、Publicスコアで上位に入っていても、最終的なPrivateスコアで順位が大きく下がる場合もあり、評価だけにとらわれすぎるとモチベーションを保つのが難しくなります。
数字はあくまでひとつの目安と捉え、「学ぶ姿勢」を大切にすることが長く続けるポイントです。
Kaggleに関するよくある質問

ここでは、Kaggleに関するよくある質問を紹介します。
Kaggleの日本語対応について
Kaggleのプラットフォームは基本的に英語で提供されており、メニューや説明文、コンペの課題文もすべて英語表記になっています。
ただし、機械翻訳ツールを使えば大まかな内容は理解できますし、日本語で解説しているブログやYouTube動画も豊富にあります。そのため英語が苦手でも、調べながら進める姿勢があればKaggleを活用することは十分可能です。
また、Kaggleは日本人ユーザーも多いので、Discussionなどで日本語のやりとりが行われていることもあります。
Kaggleのランクについて
Kaggleには、活動実績に応じて付与される5段階のランク制度があります。各カテゴリ(コンペティション・ノートブック・データセット・ディスカッション)ごとに独立したランクが設定されており、獲得メダル数などに応じて昇格していきます。
Novice
登録したすべてのユーザーに無条件で与えられる初期ランクです。
Contributor
「活動を始めたこと」を意味するランクで、初歩的なアクション(ノートブックの投稿、Discussionへの参加、データセットの公開など)を行うと自動的に昇格します。
Expert
各カテゴリで一定数の銅・銀メダルを獲得すると昇格します。
Master
コンペでゴールドメダルを獲得する、あるいは他カテゴリで銀・金メダルを多数獲得することでMasterに昇格します。称号がMaster以上になると、Kaggle外でも「実力がある」と客観的に認められやすく、アピールポイントとして活用することもできます。
Grandmaster
Kaggleにおける最高ランクです。コンペでのゴールドメダル複数獲得(うち1回はソロ参加が必要)など、取得には極めて厳しい条件が設定されています。ノートブック・データセット・ディスカッションカテゴリでも、質・量ともに大きく貢献すれば到達することも可能ですが、世界でも限られた人数しか到達できていないのが現状です。
KaggleのNotebookについて
KaggleのNotebookは、クラウド上でPythonやRのコードを記述・実行できる機能です。分析の手順をコード・図・文章でまとめることができ、他のユーザーと共有したり、公開されたNotebookを参考にしたりできます。
また、Notebookは提出や共有のたびにスコア評価がつき、評価によってメダルが付与される場合もあるので、積極的に取り組むのがおすすめです。
Kaggleのコンペ期間について
コンペによって期間は異なりますが、1〜3か月程度の期間が設定されているものが多いです。もちろん途中参加も可能ですが、1日に提出できる回数には制限があるので、できるだけ早いうちに着手した方が有利といえます。
進行中のコンペの話題について
進行中のコンペは、「Discussion」タブにさまざまなトピックが投稿されるなど、話題になりやすいです。データの見方、前処理のコツ、モデルの戦略など、参加者が自らの知見を共有しているものもあり、最新の取り組みやトレンドをキャッチする手段としても活用することができます。
まとめ
Kaggleは、実務に近いテーマに取り組みながら、自分のスキルを試せる学習環境が整っています。
初心者のうちは、英語やスコア評価など戸惑う場面もありますが、チュートリアルや他の参加者のノートブックを参考にすれば、徐々にモデル構築のコツもつかめてくるはずです。
「気になっているけど何から始めれば良いかわからない」という方は、本記事を参考に、まずはチュートリアルや終了済みコンペから気軽に触れてみてください。
また、AI関連やデータ分析関連の仕事をされている方で、キャリアを形成していきたい方には「AIジョブキャンプ」がおすすめです。AIジョブキャンプは、社会人向けの「AI教育講座」と業務委託の案件紹介をする「エージェント」サービスがセットになった無料の研修プログラムです。
長期的なスパンで自身の市場価値を高めながら、フリーランス、副業、正社員、派遣といった選択肢のなかからキャリアプランやライフスタイルに応じた働き方の実現を支援します。
また、データ分析などの知見を活かして案件を探すなら、エージェントサービス「BIGDATA NAVI」が効果的です。副業向けやフルリモート案件も豊富に揃っており、自身のスキルや働き方のスタイルに合った案件を効率よく見つけられます。
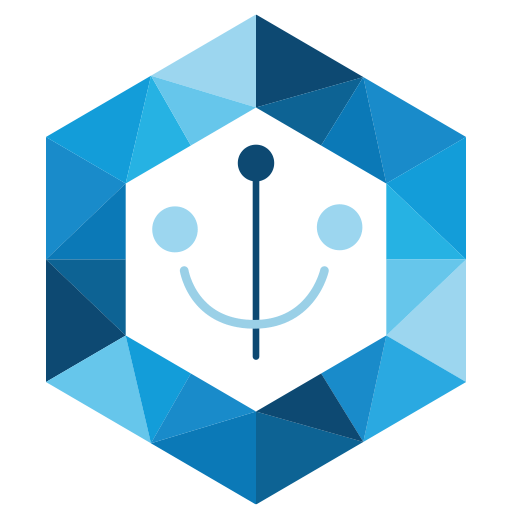
AIを仕事にするためのキャリアノウハウ、機械学習・AIに関するTopics、フリーランス向けお役立ち情報を投稿します。

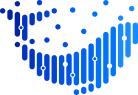 フリーランス求人を探す
フリーランス求人を探す