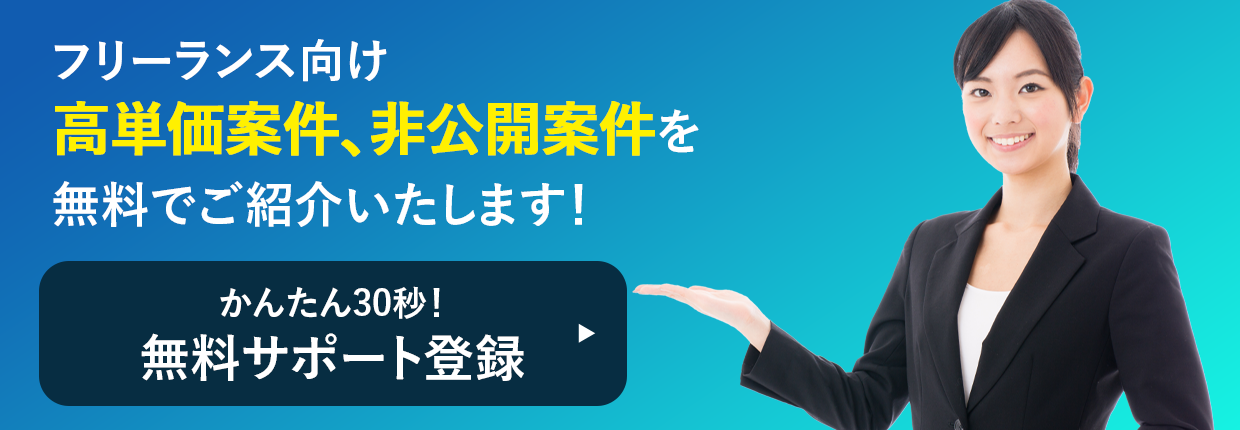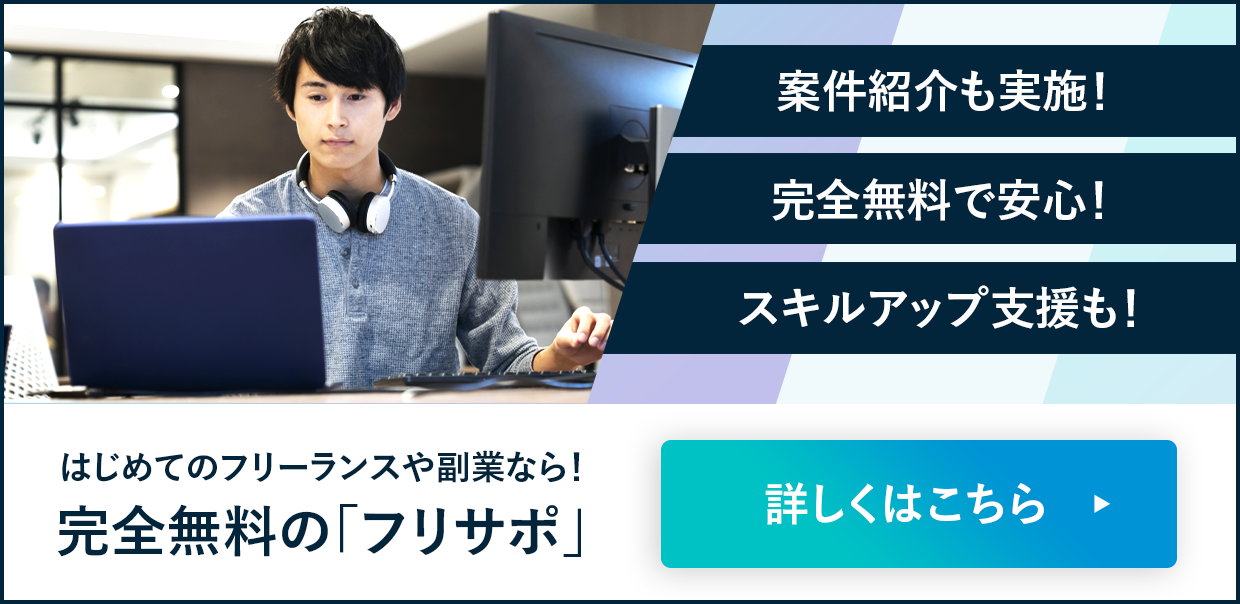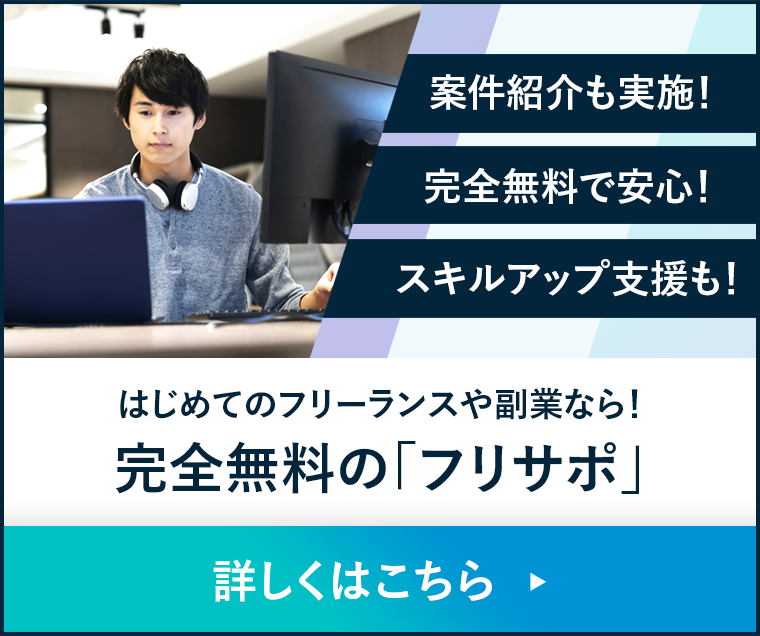データマイニングとは?主な分析手法や手順、活用事例について解説

現代のビジネス環境では、企業が保有するデータ量が日々膨大になっていますが、ただデータを集めるだけではビジネスの価値にはつながりません。
この蓄積されたデータから、有益な知見や法則性を「掘り起こす」技術が、データマイニングです。
本記事では、データマイニングの定義から、分析手法・手順・必要なスキル・そして実際の活用事例までを解説します
目次
データマイニングとは
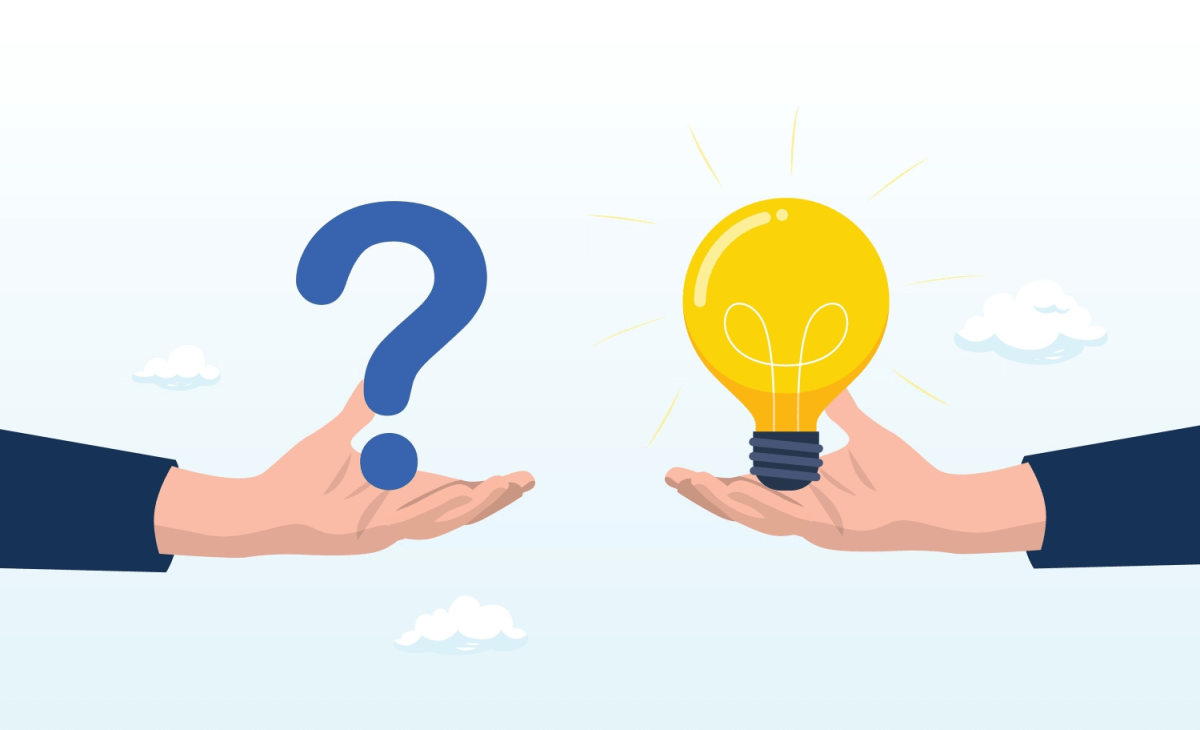
データマイニングとは、企業や組織が保有する大量のデータの中から、統計学やAI、機械学習といった技術を駆使して、膨大なデータの中からこれまで知られていなかった有益なパターン、相関関係、傾向などを発見するための分析プロセス全般を指します。
「マイニング(採掘)」の名の通り、大量に蓄積されたデータの中から「価値ある鉱脈」を見つけ出すような取り組みです。
、マーケティング戦略の立案、製品開発、業務効率化など、企業の意思決定をデータに基づいて行う、データドリブンな経営の足がかりになります。
データマイニングの主な分析手法

データマイニングには、目的に応じた様々な分析手法が存在します。
ここでは、データマイニングの代表的な手法について、「分類」「予測」「関連性の発見」という3つの目的に分けて紹介します。
分類
「分類」は、データが持つ特徴に基づいて、それぞれのデータがどのグループに属するのかを仕分ける手法です。
例えば、顧客データを「優良顧客」「一般顧客」「休眠顧客」のように分けることで、グループごとに適したアプローチを考えることができます。
クラスタリング
クラスタリングは、明確な正解がないデータ群の中から、似た特徴を持つものを自動的にグループ分けする手法です。
事前にグループの定義を与えなくても、データ間の類似性に基づいて構造を明らかにすることができるため、未知のパターンを発見するのに適しています。
予測
「予測」は、過去のデータパターンを学習することで、未来の数値や結果を予測する手法です。
将来の売上を予測したり、特定の顧客がサービスを解約する可能性を事前に察知したりすることを目的として行われることが多いです。
決定木
決定木は、データをツリー構造で表現し、条件分岐を繰り返しながら結果を予測・分類する手法です。
「もしAならばB、そうでなければC」といったルールが可視化されるため、なぜその予測結果になったのかという理由が分かりやすいのが大きな特徴です。
例えば、顧客の属性(年齢、性別、購入履歴など)から、新商品を購入するかどうかを予測するモデルを構築する際に用いることができます。
ロジスティック回帰分析
ロジスティック回帰分析は、ある事象が発生する「確率」を予測するために用いられる統計手法です。
結果が「Yes/No」「購入する/しない」「成功/失敗」のように、2つの選択肢のどちらかになるような事象の予測に適しています。
例えば、過去のデータから、顧客がキャンペーンメールを開封する確率や、特定の金融商品を契約する確率などを算出し、マーケティングの費用対効果を最大化するための判断材料として活用されます。
関連性の発見
「関連性の発見」は、一見すると無関係に見えるデータ同士の間にある関連性や共起関係を探り、新たな仮説を発見する手法です。
マーケット・バスケット分析
マーケット・バスケット分析は、「商品Aを購入した顧客は、商品Bも一緒に購入する傾向がある」といった、購買パターンを発見するための手法です。
分析結果は、関連商品の近くに陳列するクロスセル戦略や、レコメンド機能の精度向上などに活用されます。
:ABC分析
ABC分析は、売上や在庫などの指標を基準に、商品を重要度に応じてA・B・Cの3つのランクに分類する管理手法です。
「売上の8割は、全商品のうちの2割の品目が生み出している」というパレートの法則の考え方に基づく考え方で、ABC分析の結果は、在庫管理の最適化や重点的な販売促進策の立案に役立てられます。
データマイニングの手順

データマイニングを成功させるためには、一定の手順に沿って計画的にプロセスを進めることが大切です。
データマイニングの手順は、以下の通りです。
- 課題設定
- データ収集・準備
- マイニングの実行
- モデルの評価
- 導入・共有
それぞれのステップで実施する内容について、詳しく説明します。
課題設定
まず最初に、「何を明らかにしたいか」「どのような意思決定につなげたいのか」という目的と課題を明確に設定します。
例えば、「若年層の顧客離反率を10%改善したい」「新商品の売上予測精度を高めたい」といったように、数値で測定することができるものをビジネス課題として挙げてください。
この最初のステップである課題設定が曖昧になると、分析の方向性が定まらず、有益な結果を得ることができず、分析結果の活用が難しくなります。
データ収集・準備
課題設定ができたら、次はその課題解決に必要なデータを、社内の顧客管理システムや販売管理システム、Webサイトのアクセスログなど、様々なソースから集めます。
ただし、収集したデータは、そのままでは分析に使えないことがほとんどです。
そのため、欠損している値を補ったり、「株式会社」と「(株)」といった表記の揺れを統一したり、不要なデータを除外したりするデータクレンジングや前処理といった準備作業を行う必要があります。
準備作業は地味で時間のかかる工程ですが、データの質が分析結果を大きく左右するため、丁寧に行うことが大切です。
マイニングの実行
データの準備が整ったら、いよいよ分析手法を用いてマイニングを実行します。
前のステップで設定した課題に応じて、「分類」「予測」「関連性の発見」といった目的の中から最適な手法を選択し、専用のツールやPythonやRといったプログラミング言語を使ってモデルを構築します。
なお、同じ課題であっても、複数の分析手法を試してみて、どのモデルが最も良い結果をもたらすかを比較検討すると、マイニングの質を上げることに繋がります。
モデルの評価
マイニングを実行して得られた分析結果や構築したモデルが、どの程度正確か、汎用性があるか、ビジネス課題の解決に貢献できるかを評価します。
例えば、予測モデルであれば、その予測精度が実用に耐えうるレベルかの検証が必要になります。評価の結果、精度が不十分であれば、再度データ準備の段階に戻って使用するデータを変更したり、別の分析手法を試したりといった試行錯誤を繰り返します。
ここで妥協すると有効な施策を打てなくなるため、客観的な指標に基づいてモデルの有効性を厳しくチェックすることが重要です。
導入・共有
分析結果やモデルが評価をクリアしたら、実際の業務に導入します。
また、分析によって得られた知見を、専門家でない関係者にも理解できるように、グラフやレポートを用いて分かりやすく可視化し、共有します。このように、分析結果を組織全体で活用していくことで、データドリブンな経営が組織全体に根付いていくのです。
データマイニングに必要なスキル

データマイニングを実践するには、以下のような専門的な知識とスキルが求められます。
- 統計学、機械学習の知識
- プログラミングスキル
それぞれ詳しく解説していきます。
統計学、機械学習の知識
データマイニングの基盤となるのが、統計学と機械学習の知識です。
統計学は、データの傾向を数値的に理解し、ばらつきや相関関係を把握するために不可欠です。
実際、「どの変数が売上に最も影響しているのか」を見極める回帰分析や、「購買行動が似ている顧客をグループ化する」クラスタリングなど、すべての分析は統計的な考え方の上に成り立っています。
一方で、機械学習の知識は、統計学をさらに発展させた「データから自動的に学習する技術」を扱います。あらかじめルールを設定するのではなく、過去のデータを学習してパターンを抽出し、未知のデータに対しても予測や分類を行うのが特徴です。
代表的な手法には、条件分岐を可視化する決定木や、複数のモデルを組み合わせて精度を高めるランダムフォレストなどがあります。
このような手法が使いこなせるようになると、単なる「データの可視化」ではなく、将来の需要予測や顧客離脱予測、レコメンドエンジンの構築といった応用分析が可能になります。
プログラミングスキル
データマイニングでは、単に分析ツールを操作するだけでなく、「膨大なデータの前処理」「モデルの構築・検証」「結果の可視化」といった一連のプロセスを自動化する必要があります。
例えば、PythonやRといったプログラミング言語を使いこなせると、データの加工・処理から、モデル構築、結果の可視化までを効率的に行うことができます。
また、SQLのようなデータベース言語も理解しておくと、大規模データから必要な情報を効率的に抽出でき、より複雑で大規模な分析プロジェクトに対応できるようになるため、エンジニアとしての市場価値が高まりやすいといえます。
データマイニングの活用事例
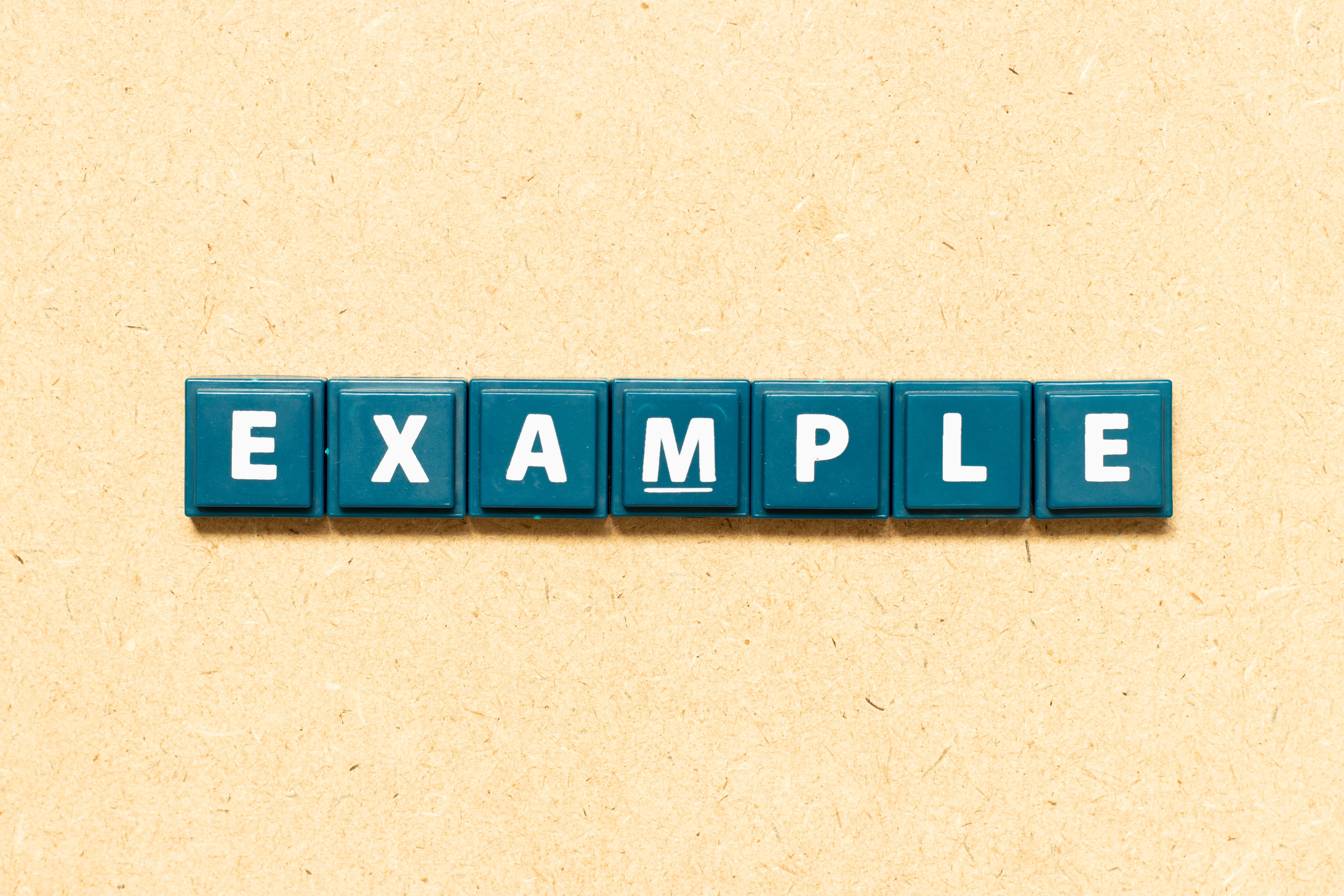
データマイニングは、特定の業界に限らず、幅広い分野で意思決定の高度化や業務効率化に役立っています。
ここでは、具体的な活用事例を「金融」「製造」「医療」「教育」「小売」の5つの業界に分けて紹介します。
- 金融業界:金融:顧客・取引データの分析
- 製造業界:設備機器の分析
- 医療業界:診療データの分析
- 教育業界:成績データの分析
- 小売業界:マーケティング施策の立案
それぞれ詳しくみていきましょう。
金融業界:金融:顧客・取引データの分析
金融機関では、データマイニングを用いた「リスク管理の高度化」と「マーケティング施策の最適化」が進められています。
例えば、クレジットカード会社では、利用日時、場所、金額などの顧客の取引履歴を学習したモデルが取引データをリアルタイムで監視しています。
これにより「普段は国内利用しかない顧客が深夜に海外で高額決済を行った」といった通常とは異なる行動を即座に検知することができ、不正被害が未然に防がれているのです。
また、銀行では顧客ごとに最適な金融商品をレコメンドするモデルの構築により、提案精度の向上と営業効率の改善を同時に実現しています。
:製造業界:
製造業では、工場の生産性向上と品質管理のためにデータマイニングが活用されており、その代表的な例が「予知保全」です。
工場では、生産ラインにある機械に取り付けられたセンサーが、稼働時の振動、温度、圧力といったデータを常時収集します。
これらの時系列データを分析することで、「故障が発生する数日前に、特有の微細な振動パターンが現れる」のような法則を発見します。
この兆候を捉えた時点でアラートを発し、計画的に部品交換を行うことで、生産ラインの突然の停止による大きな損失が回避できるのです。
また、製品の画像データをAIで分析し、人間の目では見逃されてしまうような微細な傷を自動で検出する品質検査なども実用化されています。
医療業界:診療データの分析
医療分野では、診断支援や個別化医療の実現にデータマイニングが貢献しています。
例えば、過去の膨大なレントゲンやCTスキャン画像をAIに学習させ、医師の診断を補助するシステムの開発が進められています。人間の目では見分けるのが難しい微小ながんの疑いがある箇所をAIが自動的に指摘することで、病気の早期発見び繋がることが期待されています。
また、患者の遺伝子情報や過去の治療データに加え、治験データ、副作用報告などまで幅広く分析し、「特定の遺伝子を持つ患者群には、薬剤Aよりも薬剤Bの方が副作用が少なく効果が高い」といった知見を得ることで、患者属性に応じた最適な治療方針を提示する「プレシジョン・メディシン」の実現が進められています。
教育業界:成績データの分析
教育分野では、生徒一人ひとりの学習効果を最大化するためにデータマイニングが活用されています。
eラーニングシステムでは、生徒の学習ログを分析し、どの問題を、どれくらいの時間で解き、正解したかを詳細に把握します。
これにより「特定の単元でつまずいている生徒は、その手前の基礎単元の理解が不十分である」といったパターンを特定し、自動的に復習問題を提示する「アダプティブラーニング」が可能になっています。
小売業界:マーケティング施策の立案
小売・EC業界では、購買履歴やWeb行動データを分析し、販売戦略や在庫管理の最適化に活用しています。
例えば、スーパーマーケットでは、POSデータをもとに「一緒に購入される商品の組み合わせ」を探るマーケット・バスケット分析が導入されています。
この分析により「おむつを買う人はビールも一緒に買う傾向がある」という事実が発見され、棚配置を変えた結果、関連商品の売上が20%以上増加したという事例もあります。
まとめ
この記事では、データマイニングとは何かという基本的な概念から、具体的な分析手法、プロジェクトを進める手順、そして様々な業界での活用事例までを網羅的に解説しました。
AIや機械学習技術の進化に伴い、データから価値を生み出せる専門人材の需要はますます高まっています。データマイニングのスキルを身につけることは、これからの時代を生き抜くエンジニアやデータサイエンティストにとって大きな強みとなるはずです。
弊社が運営する「BIGDATA NAVI」は、データサイエンスやAI開発といった最先端領域に特化したフリーランスエージェントです。
データマイニングのスキルを活かせる高単価案件や、キャリアアップにつながるチャレンジングなプロジェクトを多数保有しています。専門知識を持つコンサルタントが最適な案件を提案しているので、データ活用のプロフェッショナルとして活躍したい方は、ぜひ活用してみてください。
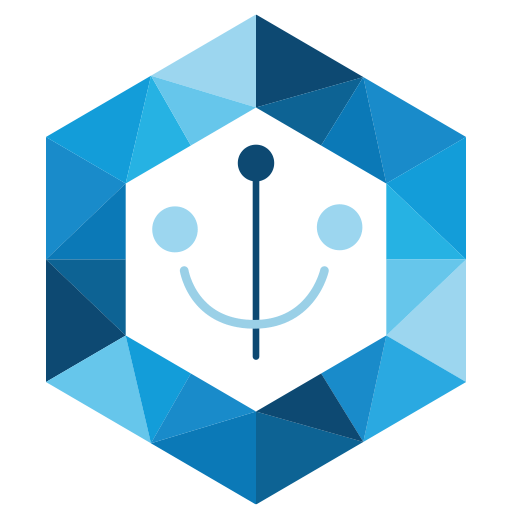
AIを仕事にするためのキャリアノウハウ、機械学習・AIに関するTopics、フリーランス向けお役立ち情報を投稿します。

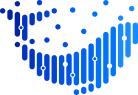 フリーランス求人を探す
フリーランス求人を探す