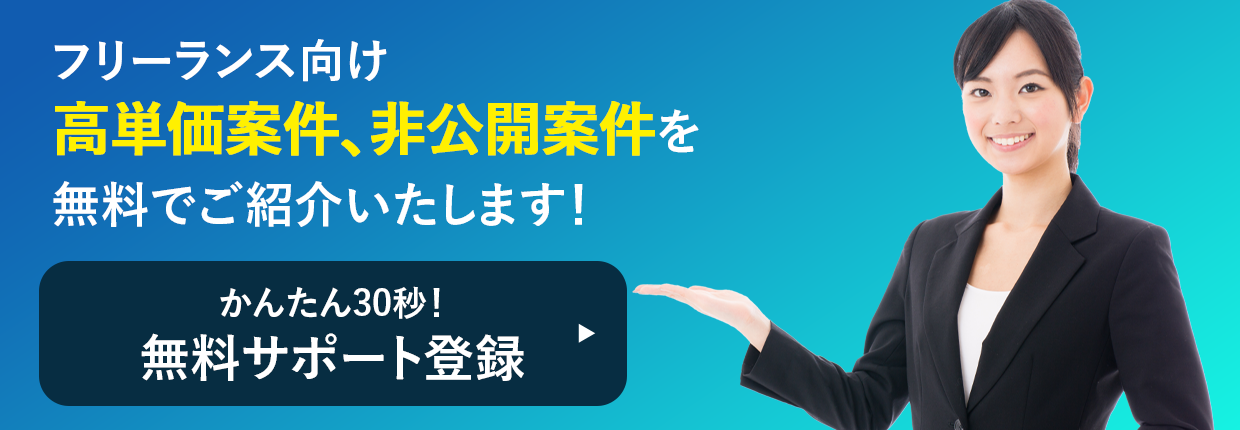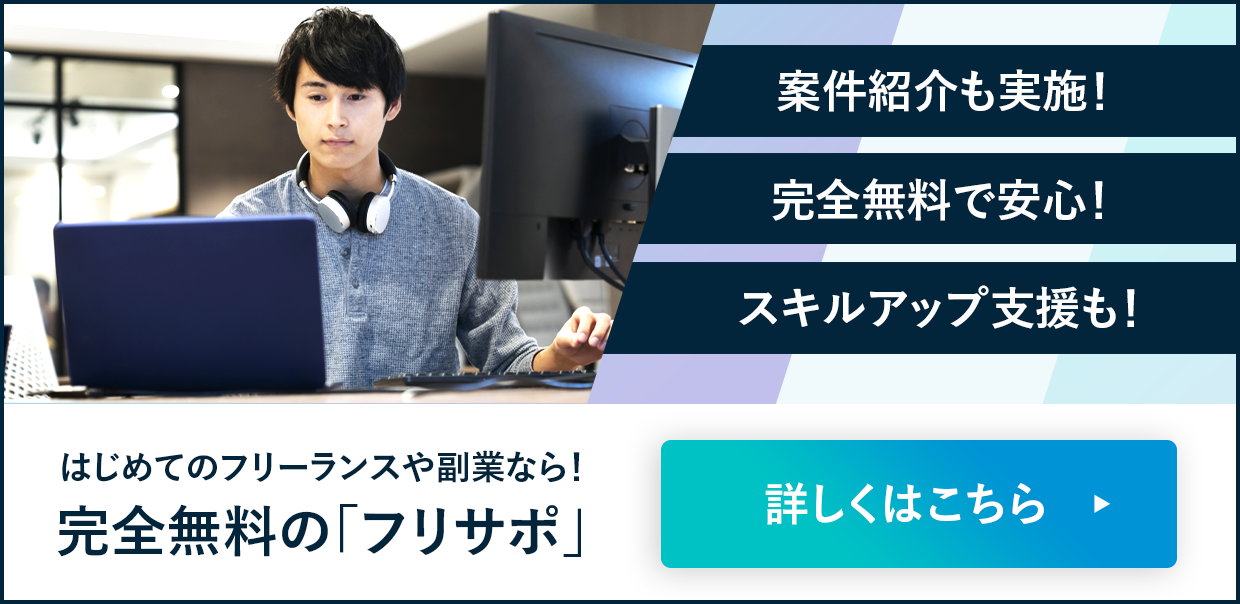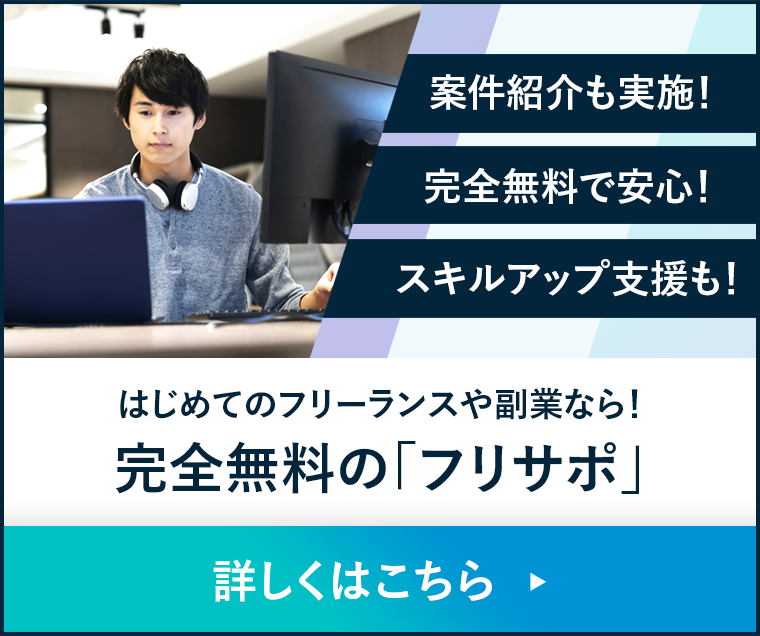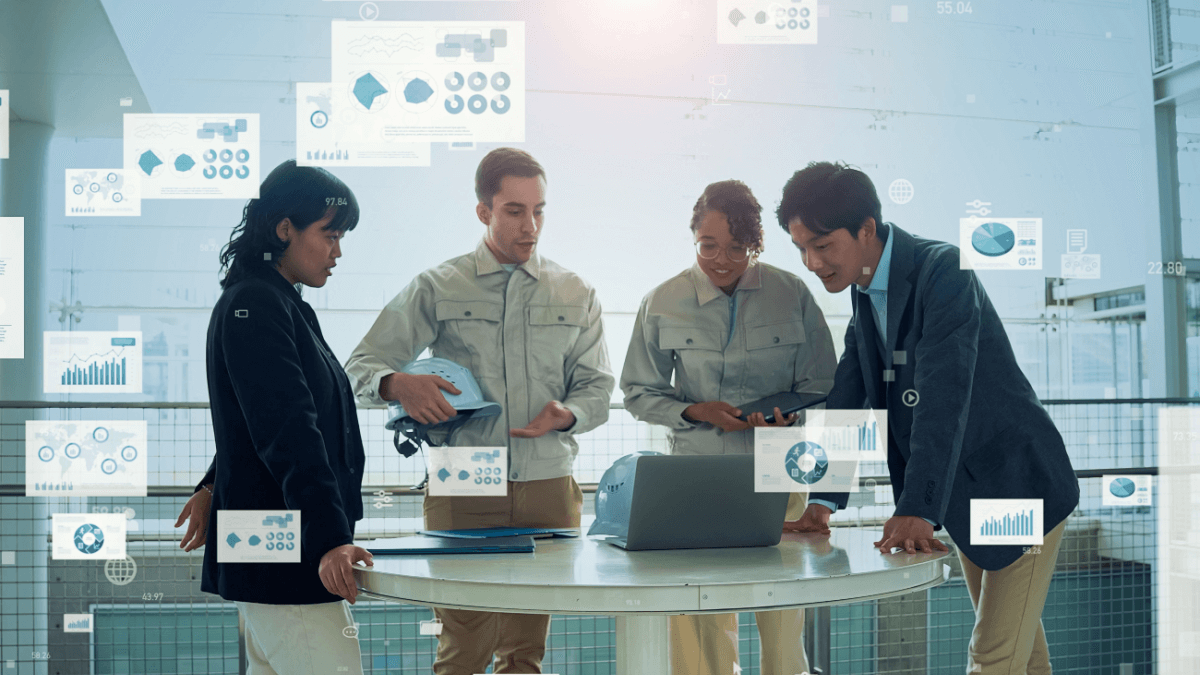ロボット工学技術者・ロボットエンジニアとは?仕事内容や求められるスキルについて解説

現代では、製造業や医療、サービス業など、あらゆる分野でロボットの活用が進んでいます。その中心で活躍するのが「ロボット工学技術者・ロボットエンジニア」です。最先端技術を駆使して、社会の課題を解決する新しいロボットを研究・開発する専門家であり、その需要は年々高まっています。
しかし、具体的にどのような仕事をしていて、どんなスキルが求められるのか、詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。
本記事では、ロボットエンジニアの仕事内容を分かりやすく分解し、求められるスキルやおすすめの資格、キャリアパスまでを網羅的に解説します。
目次
ロボット工学技術者・ロボットエンジニアとは?
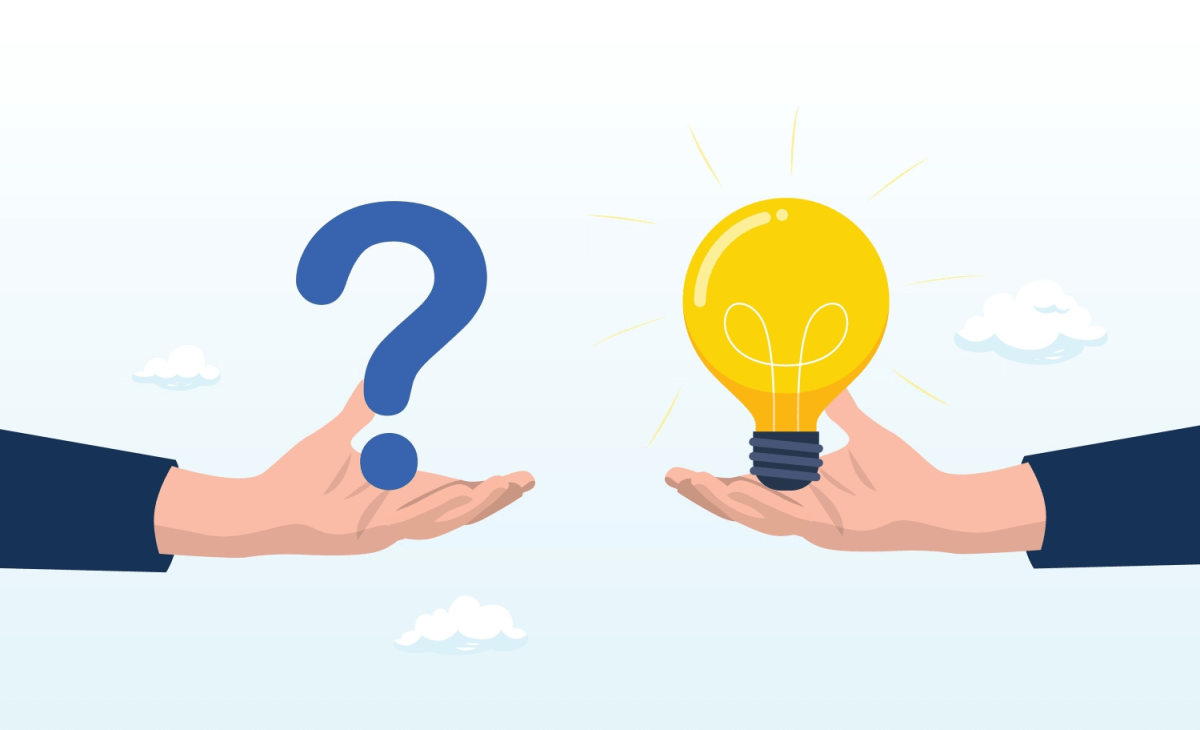
ロボット工学技術者・ロボットエンジニアとは、AIや機械工学、電子工学といった幅広い分野の知識を統合し、様々な目的を持つロボットの研究、設計、開発、製造、メンテナンスまでを手掛ける技術者の総称です。
その活躍の場は、工場の生産ラインで稼働する産業用ロボットから、家庭用のお掃除ロボット、医療・介護現場を支援するロボット、さらには災害救助や宇宙探査といった極限環境で働くロボットまで多岐にわたります。
単に機械を組み立てるだけでなく、ロボットに知能を与え、目的に応じた最適な動きをさせるためのソフトウェア開発まで行う専門性が高くやりがいのある仕事です。
ロボット工学技術者・ロボットエンジニアの仕事内容

ロボット開発は、多くの場合、チームを組み、それぞれの専門分野を分担して一つのロボットを完成させます。
ここでは、それぞれの専門分野が具体的にどのような役割を担っているのかを詳しく解説していきます。
メカ系(骨格・ボディ担当)
メカ系エンジニアは、ロボットの骨格や外装といった物理的な「身体」を設計・開発する役割を担います。
主な業務は、3D-CADを用いてロボットの形状や材質、関節などの機構を設計することです。
また、設計したロボットが想定通りに動くか、必要な強度を満たしているかをコンピューター上でシミュレーションし、検証を重ねることもメカ系の役割です。
機械工学や材料力学の知識を基に、ロボットの耐久性や運動性能といった基本性能を決定づける、ロボット制作の根幹を支える重要なポジションです。
エレキ系(神経・循環器担当)
エレキ系エンジニアは、ロボット全体に電力を供給し、各パーツ間で信号をやり取りするための「神経網」や「血管」にあたる電子回路を設計します。
具体的には、モーターやセンサー、コンピューターといった電子部品を動かすための電子基板(プリント基板)を開発するのが主な業務です。
電源回路や駆動回路、信号処理回路などを一つの基板上に設計し、ロボットが安定して動作するための構築のため、電気・電子工学に関する深い専門知識が不可欠です。
センサ系(五感担当)
センサ系エンジニアは、ロボットが周囲の状況を把握するための「五感」の役割を果たす、各種センサーをシステムに組み込む専門家です。
主な業務は、ロボットの目的に応じて、カメラ(視覚)やマイク(聴覚)、距離センサー(触覚)といった多種多様なセンサーの中から最適なものを選定し、その性能を評価することです。
また、センサーが取得した情報を、ロボットの脳である「知能・制御系」が処理できる電気信号に変換する役割も担います。
知能・制御系(大脳・小脳担当)
知能・制御系エンジニアは、ロボットの「脳」として振る舞いを決定するソフトウェアを開発する、プロジェクトの中核を担う役割です。
業務は大きく二つに分かれており、ひとつはセンサーからの情報をもとに状況を認識・判断する「知能」部分の開発。もうひとつは、その判断に基づき、モーターなどをどのように動かすかを指令する「制御」部分の開発です。
近年ではAI技術の活用も進んでいることから、C++やPythonといったプログラミング言語を駆使して、ロボット自身に人格そのものを創り出すこともあります。
駆動系(筋肉・手足担当)
駆動系エンジニアは、脳からの指令を実際の「動き」へと変換するモーターなどの駆動装置(アクチュエータ)を扱います。
主な業務は、ロボットに求められるパワーやスピード、精度に応じて、最適なモーターやシリンダーを選定・開発することです。
また、その力をロボットアームの関節などに効率よく伝えるための、歯車(ギア)といった伝達機構の設計も担当します。
ロボット工学技術者・ロボットエンジニアに求められるスキル

最先端技術の結晶であるロボットを開発するには、特定の分野に特化した深い専門知識と、それを統合するための幅広いスキルが求められます。
ここでは、ロボットエンジニアとして活躍する人に求められる5つのスキルについて解説します。
ロボット工学の知識
ロボットエンジニアにとって、ロボット工学の体系的な知識は全ての基本となります。
ロボット工学は、機械工学、電気・電子工学、情報工学(特にプログラミングやAI)という3つの主要な学問領域が融合したもので、以下のようなものがあります。
- ロボットの腕や脚の動きを数学的に解析する「ロボット・キネマティクス(運動学)」
- ロボットに働く力と動きの関係を扱う「ロボット・ダイナミクス(動力学)」
- ロボットを意のままに動かすための「制御工学」
これらの基礎知識がなければ、ロボットの設計や動作プログラムの作成は困難なので、大学や専門学校での学習や、専門書を通じた継続的な学習が求められます。
電気・電子工学の知識
ロボットは電気で動く精密機械であるため、電気・電子工学の知識も必要になります。
モーターを制御したり、センサーからの信号を読み取ったりするためには、回路図の読解や作成能力、オシロスコープなどを用いた計測・評価技術、基板設計の知識などが必要です。
また、電力供給やノイズ対策に関する知識も、ロボットを安定して動作させるためには重要になります。
たとえメカ系のエンジニアであっても、電気系のチームと円滑に連携するために、基礎的な知識は身につけておくべきといえるでしょう。
CADスキル
CAD(Computer-Aided Design)は、コンピューター上で製品の設計や製図を行うためのツールであり、ロボットの骨格や外装を設計するメカ系のエンジニアにとっては必須のスキルです。
3D-CADを用いてロボットの部品を立体的に設計し、それらを組み立てた際の部品同士の干渉がないかを確認したり、強度や動きをシミュレーションしたりします。
また、作成した設計データはそのまま3Dプリンターや工作機械に送り、実際の部品製造に使うことも可能です。
さらに、実務では「SolidWorks」や「AutoCAD」などのツールを自在に使いこなせるレベルの人材を求められることが多いです。
センサ類の評価・選定に関する知識
ロボットが周囲の環境を認識するために不可欠なセンサーですが、画像、音声、距離、温度、力などその種類は多岐にわたります。
ロボット開発においては、開発目的や用途に応じて、無数にあるセンサーの中から最適なものを選定することが求められるため、センサ類の選定に関する知識と経験が必要です。
また、ロボットの性能を最大限引き出すためにも、選定したセンサーの性能(精度、応答速度、耐久性など)を評価し、特性を理解した上でシステムに組み込む能力も必要になります。
コミュニケーション能力
ロボット開発は、機械、電気、情報など、異なる専門分野を持つエンジニアたちが協力して進めるチームプロジェクトです。
そのため、自分の専門分野について分かりやすく説明したり、他の分野のエンジニアの意見を正しく理解したりするためのコミュニケーション能力が求められます。
また、ロボットに求められる要件を正確に引き出すヒアリング能力も、クライアントの目的を達成するために必要になります。
ロボット工学技術者・ロボットエンジニアにおすすめの資格
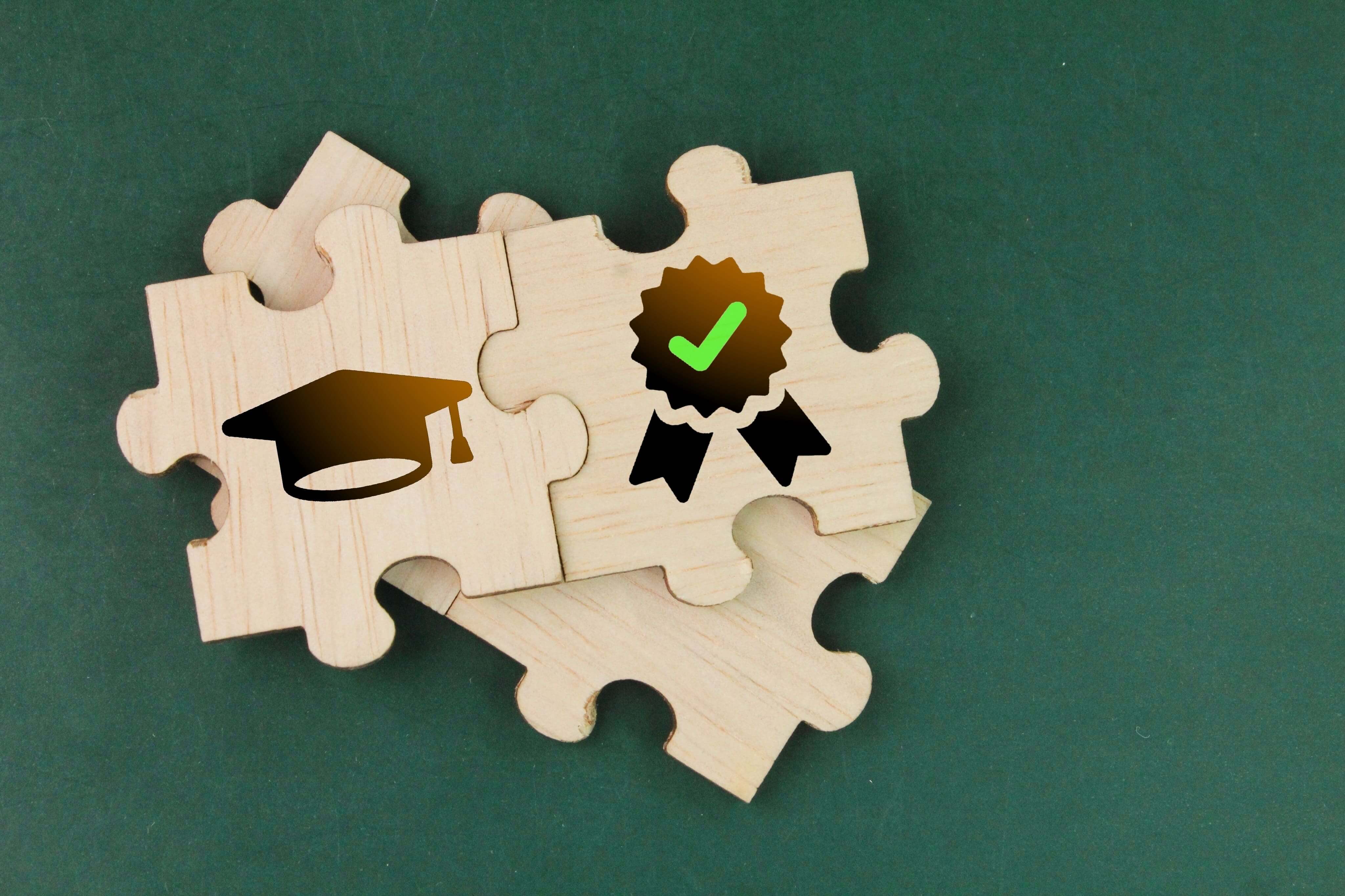
ロボットエンジニアになるために必須の資格というものはありませんが、自身のスキルレベルを客観的に証明し、キャリアアップや転職を有利に進める上で役立つ資格はいくつか存在します。
ここでは、ロボットエンジニアにとって特におすすめの4つの資格を紹介します。
情報処理技術者試験
情報処理技術者試験は、ITに関する知識・技能を認定する国家試験で、ロボットの「知能・制御分野」で活躍したいエンジニアにおすすめの資格です。
試験には以下の3種類があり、受験者のレベルや専門性によって選択することができます。
- 基本的なIT知識を問う「基本情報技術者試験」
- より高度なシステム設計能力が問われる「応用情報技術者試験」
- 組込みシステムの専門知識を証明する「エンベデッドシステムスペシャリスト試験」
これらの資格は、プログラミング能力やシステム開発に関する深い理解度を示す根拠となるので、副業案件の獲得はもちろん、就職・転職でも有利になりやすいです。
機械設計技術者試験
機械設計技術者試験は、一般社団法人日本機械設計工業会が認定する民間資格で、ロボットの「メカ系(骨格・ボディ)」や「駆動系」を担当するエンジニアにおすすめです。
試験は1級から3級まであり、機械力学、材料力学、製図、制御工学といった、機械設計に必要な知識が幅広く問われます。
この資格を取得することで、機械設計に関する体系的な知識と応用力を持っていることをアピールできるため、案件獲得の際に有利になりやすいといえます。
電気主任技術者試験
電気主任技術者試験は、事業用電気工作物の工事、維持、運用の保安監督者になるための国家資格です。
ロボットそのものというよりは、産業用ロボットシステムの導入や保守に関わる場合や、大規模なロボットシステムの電源設備を扱う際に役立つ資格といえます。
CAD利用技術者試験
CAD利用技術者試験は、CADを扱う技術者のスキルを証明するための民間資格です。
2次元CADと3次元CADの試験がありますが、ロボット工学においては3次元CADのスキルを証明する「3次元CAD利用技術者試験」の所持者は評価されやすいです。
設計スキルやモデリング能力を客観的に示すことで、即戦力として設計業務に貢献できることをアピールできます。
ロボット工学技術者・ロボットエンジニアに向いている人

ロボット工学技術者・ロボットエンジニアとしてキャリアを築いていくためには、特定の資質や興味関心が求められます。
ここでは、ロボットエンジニアに向いている人の特徴を4つの観点から解説していきます。
ロボットや最先端技術が好き
ロボットエンジニアに向いている人の基本かつ非常に重要な素養は、何よりもまずロボットやメカ、そしてAIなどの最先端技術が心から好きであることです。
「好きこそものの上手なれ」という言葉通り、純粋な好奇心や探究心は非常に強いモチベーションになります。幼い頃からアニメや映画に登場するロボットに憧れていた、機械の仕組みを分解して調べるのが好きだった、というような経験を持つ人は向いているといえるでしょう。
ものづくりが好き
ロボット開発は、アイデアや理論といった目に見えないものを、実際に動く「モノ」として形にする仕事です。
そのため、自分の手で何かを創り出す「ものづくり」そのものが好きな人に向いています。
設計図を基に部品を組み立てたり、プログラムを書いてロボットが思い通りに動いた瞬間に達成感を覚えたりする人は、この仕事にやりがいを感じやすいといえるでしょう。
最新技術を学習するのに抵抗がない
ロボット工学の分野は日進月歩で、AI、センサー技術、材料工学など、関連する技術は常に進化し続けています。昨日まで最先端だった技術が、今日にはもう古くなっているということは日常茶飯事です。
そのため、ロボットエンジニアとして第一線で活躍し続けるには、常に新しい知識やスキルを学び続ける姿勢が必要です。
学生時代の勉強だけで満足するのではなく、専門書を読んだり、国内外の論文に目を通したり、セミナーに参加したりと、自発的に学習を続けることに抵抗がない人はこの仕事に向いているといえます。
チームワークを大切にできる
前述しましたが、ロボット開発は様々な専門分野のエンジニアが集まって行うチームプレイです。メカ、エレキ、ソフトウェアなど、各分野のプロフェッショナルがそれぞれの役割を果たし、協力し合って初めて一つのロボットが完成します。
そのため、他のメンバーの意見に耳を傾け、尊重し、円滑なコミュニケーションを取りながらプロジェクトを進められる協調性が求められます。
お互いの進捗を共有し、問題が発生した際には知恵を出し合えるような、チームワークを大切にできる人は、プロジェクトに必要な人材として重宝されやすいです。
ロボット工学技術者・ロボットエンジニアになるには?

ロボット工学技術者・ロボットエンジニアは専門性が高い職種であるため、計画的なキャリアパスの構築が必要です。
大学などで専門知識の基礎を固めてから就職するルートが王道ですが、他の職種からのキャリアチェンジや、社会人になってから学び直して転職する方法もあります。
ここでは、ロボットエンジニアになるための方法を5つ紹介します。
工学系の大学や専門学校で学ぶ
ロボットエンジニアになるための最も一般的なルートは、大学や大学院、専門学校でロボット工学に関連する専門知識を学ぶことです。
ロボット開発には機械工学・電気電子工学・情報工学といった幅広い知識が必要であり、独学で目指すのは困難ですが、教育機関ではこれらの学問を体系的に学ぶことができます。
特に、大学院まで進学してロボット開発のプロジェクトに携わった経験は、就職活動において高く評価されやすいです。
おすすめの学部
ロボットエンジニアを目指す上でおすすめの学部は、以下のとおりです。
- 機械工学科
- 機械システム工学科
- 電気電子工学科情報工学科
- コンピュータサイエンス学科
- ロボティクス学科
- 知能機械工学科
システムエンジニアを経てロボットエンジニアに転職する
IT業界でシステムエンジニア(SE)として働いた経験がある場合は、ロボットエンジニア(特に知能・制御系)への転職がしやすいといえます。
SEとして培ったプログラミングスキルやシステム開発のプロジェクトマネジメント経験は、ロボットのソフトウェア開発において大いに役立ちます。
特に、C++やPythonといったロボット開発で多用される言語や、ROS(Robot Operating System)などのプラットフォームに関する知識があると、有利になりやすいです。
資格取得後に未経験可の求人に応募する
学歴やエンジニアがなくても、「情報処理技術者試験」や「CAD利用技術者試験」といった関連資格を取得し、学習意欲と知識をアピールできれば、ロボットエンジニアになれる可能性はあります。
しかし、学歴や経験が前提の仕事が大半なので、「未経験可」や「ポテンシャル採用」を掲げている企業を見つける必要があります。あるいは、人手不足が深刻な中小のメーカーや、研修制度が充実している企業では、未経験者を採用してくれる可能性もあります。
プログラミングスクールを利用する
近年、社会人向けのプログラミングスクールの中には、AIやIoT、ロボット制御に特化したコースを設けているところも増えてきました。
これらのスクールを利用すれば、働きながらでも効率的にロボット開発に必要なプログラミングスキルや専門知識を学ぶことができます。
独学では挫折しがちな環境構築や、実践的なカリキュラム、現役エンジニアによるメンタリングなどが受けられる点が魅力です。
また、スクールによっては、ポートフォリオの作成支援や、企業への転職サポートまで行ってくれる場合もあるので、短期間でキャリアチェンジを目指す方には特におすすめです。
目指すべき就職先
ロボットエンジニアの就職先は多岐にわたりますが、主な就職先としては以下のような場所があります。
◼︎大手製造業具体例:自動車メーカー、電機メーカー、産業用ロボットメーカーなど。
特徴:開発規模が大きく、資金力も豊富なため、大規模な開発プロジェクトに携われる。
◼︎特化型ベンチャー企業
具体例:医療、介護、物流、農業など、特定の分野に特化したロボットを開発する企業。
特徴:最新技術を積極的に取り入れたスピーディーな開発が可能。
◼︎ロボットシステムインテグレータ(SIer)
具体例:各メーカーのロボットを組み合わせて、工場の自動化ラインなどを構築する企業。
特徴:特定のメーカーに縛られず、様々なロボットや周辺機器を扱うため、幅広い知識と応用力が身につけられる。
◼︎大学・公的研究機関
具体例:大学の研究室、産業技術総合研究所(産総研)など。
特徴:企業の製品開発とは異なり、より基礎的な研究や、5年後、10年後を見据えた次世代のロボット技術開発に携わることが可能。
ロボット工学技術者・ロボットエンジニアのよくある質問

ここでは、ロボットエンジニアを目指す方々からよく寄せられる質問について、Q&A形式でお答えします。
需要はあるの?
ロボット工学技術者・ロボットエンジニアの需要は非常に高いといえます。
製造業の工場や物流倉庫では自動化が急速に進んでおり、産業用ロボットの需要は拡大し続けています。
また、医療・介護現場での負担軽減、農業の効率化、サービス業での接客など、これまで人の手で行われてきた作業を代替・支援するサービスロボットの市場も急成長しています。
このように、社会のあらゆる場面でロボットの活用が期待されており、その開発を担うロボットエンジニアは、今後ますます必要とされることが予想されています。
平均年収は?
ロボットエンジニアの平均年収は、一般的に400万円〜800万円程度が相場とされています。
ただし、AIや高度な制御技術など、最先端の専門知識を持つエンジニアや、プロジェクト全体を管理するマネジメント能力を持つエンジニアは、年収1,000万円を超えることもあります。
将来性はあるの?
あります。
むしろロボットエンジニアは、極めて将来性の高い職業であると言えます。
スマートファクトリー、自動運転、ドローン配送、遠隔手術など、未来の社会を形作るテクノロジーの多くは、ロボット技術が中核をなしていると言っても過言ではありません。
また、単純作業はAIやロボットに代替されると言われる時代において、そのAIやロボット自体を開発するエンジニアの仕事がなくなる可能性は極めて低いです。
まとめ
本記事では、ロボット工学技術者・ロボットエンジニアの仕事内容から、求められるスキル、キャリアパス、将来性までを詳しく解説しました。
ロボットエンジニアは、機械、電気、情報といった幅広い専門知識を結集し、社会に貢献するロボットを創造する、非常に専門性が高くやりがいのある仕事です。
データサイエンスやAI分野に特化したエージェントサービス「BIGDATA NAVI」では、ロボット開発におけるAI実装やデータ解析といった案件を幅広く取り扱っています。
ロボット工学技術者・ロボットエンジニアの仕事を探している方は、BIGDATA NAVIの活用も検討してみてください。
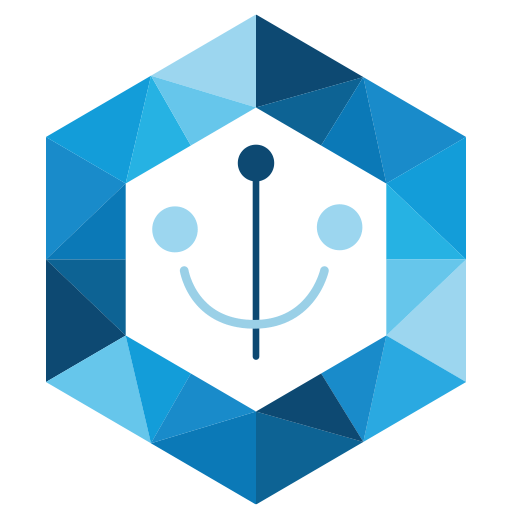
AIを仕事にするためのキャリアノウハウ、機械学習・AIに関するTopics、フリーランス向けお役立ち情報を投稿します。

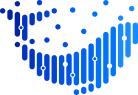 フリーランス求人を探す
フリーランス求人を探す